「売上や業績を伸ばしたい」と考えたとき、施策のひとつとして検討されるのが顧客満足度の向上ではないでしょうか。
顧客満足度向上によってリピート顧客の獲得だけでなく、口コミの高評価や他人から勧められることで自然と新規顧客獲得にも繋がります。
その結果、新規顧客を開拓するために多くのリソースを割く必要もないため、別事業に注力できるかもしれません。
本記事では顧客満足度を向上させる5つのポイントを中心に、評価方法や成功事例について解説します。
ポイントや事例からコツを掴み、ぜひ、顧客満足度の向上に繋げていきましょう。
顧客満足度(CS)とは「提供サービスを利用するときに感じる満足感」
顧客満足度とは、企業が提供する商品やサービスに対する顧客の満足度を指します。
CS(Customer Satisfaction)や、消費者・お客様満足度などとも呼ばれます。
顧客満足度を向上させるメリットは、企業の売上や利益の増加、顧客の定着率の向上、ブランドイメージの向上です。
顧客満足度を向上させるためには、顧客のニーズを理解し、それを満たす商品やサービスを提供することが重要です。
また、顧客とのコミュニケーションを密にし、顧客からのフィードバックを積極的に取り入れることも欠かせません。
顧客満足度の評価方法
顧客満足度を評価する方法は、以下の2つが一般的です。
- アンケート調査の実施
- 顧客からの直接ヒアリング
それぞれ、詳しく解説していきます。
アンケート調査の実施
アンケート調査は、顧客満足度を評価する上で非常に有効な方法の一つです。
多くの意見を聞くことができ、商品やサービスを改善するきっかけにもなるでしょう。
アンケート調査には「定量調査」と「定性調査」の2種類あります。
定量調査とは、顧客の意見や感想を数値で表すための調査方法です。意見や感想を数値化し、満足度を定量的に把握できます。
一方、定性評価は、意見や感想を自由に述べてもらうことで、顧客のニーズや課題を深く理解する方法です。
アンケート調査を行う際には、目的に応じて、定量調査と定性調査を組み合わせて行うことで、より効果的な調査を行えます。
参考:顧客満足とは:CS向上のアプローチと調査の活用|公益財団法人日本生産本部
顧客から直接ヒアリング
顧客とのヒアリングとは、顧客と直接会って、商品やサービスに対する満足度を聞く方法です。
普段から顧客と接する担当者が、通常業務と合わせてヒアリングできるため、リサーチにかかる予算や労力などのリソースを最小限にできます。
アンケート調査は多くの顧客から情報を収集できるのに対し、ヒアリング調査は顧客の情報量は少ないもののニーズを深く理解できるため、目的や予算に合わせて評価方法を選択しましょう。
顧客満足度を向上させる5つのポイント
顧客満足度を向上させるポイントは、数多くあります。
本章では、その中でも特に重要な下記5つのポイントをピックアップして紹介します。
- 顧客の期待を上回るサービスを提供する
- 衛生要因・動機付け要因を分析する
- CRMやSFAを導入し効率化を図る
- 従業員のモチベーションを向上させる
- 顧客間でのコミュニティーを形成する
それぞれ詳しく解説していきます。
1.顧客の期待を上回るサービスを提供する
顧客が期待する以上のサービス提供は、顧客満足度を大きく向上させるポイントのひとつです。
付加価値をつけるポイントとしては「カスタマーサービスの充実」や「商品やサービスの購入方法の簡略化」など商品やサービス以外の部分で期待を超えるような工夫が挙げられます。
顧客の期待を上回るサービスを提供することで、企業のファンとなる可能性があります。
顧客がファンになることで、同業他社がより良い商品やサービスを提供したとしても自社から離れないため、長期的な利益を生むかもしれません。
「顧客の期待値を上回るサービス提供」を心がけておきましょう。
2.衛生要因・動機付け要因を分析する
人間のモチベーションを高める要因は、以下の2つに分かれるとされています。
- 衛生要因
- 動機付け要因
これは、ハーズバーグの二要因理論と呼ばれ、アメリカの心理学者であるフレデリック・ハーズバーグによって提唱された、動機付けに関する理論です。
衛生要因とは、不満の原因となる要因です。
例えば、給与や労働条件、仕事の安全性などは、衛生要因に該当します。
衛生要因が不十分だと不満を抱くことになりますが、十分であってもモチベーションは高まりません。
動機付け要因とは、モチベーションを高める要因です。
例えば、仕事の達成感や責任感、成長の機会などは動機付け要因に該当します。
動機付け要因が十分だと、モチベーションが高まり、仕事にやりがいを感じます。
顧客満足度においても、衛生要因と動機づけ要因は同様です。
衛生要因が不十分だと、顧客は不満を抱くことになりますが、十分であっても顧客満足度は高まりません。
そのため、顧客満足度を高めるためには、動機づけ要因を満たす必要があります。
衛生要因と動機づけ要因をそれぞれ分析し、それらを満たすことがポイントとなります。
参考:ハーズバーグの研究方法に関する一考察 : 実効性の高いやる気のマネジメントの実現に向けて|名古屋市立大学
3.CRMやSFAを導入し効率化を図る
顧客満足度を向上させるポイントとしてCRMやSFAを導入し、効率化を図ることもポイントです。
CRM(Customer Relationship Management)とは、顧客との関係を管理するためのシステムです。
顧客の情報を一元管理することで、ニーズの分析と理解が深まります。
SFA(Sales Force Automation)とは、営業活動を自動化するためのシステムです。
営業活動を自動化することで、営業担当者の負担を軽減し、より効率的に営業活動を行うことができます。
これらを導入することで、顧客ニーズおよび営業の最適化が図れるため、より魅力的なサービスを顧客に提供できるでしょう。
4.従業員のモチベーションを向上させる
従業員のモチベーションが高ければ、顧客に良いサービスを提供しようとする意欲が高まります。
顧客満足度の向上には少し遠回りに感じるかもしれませんが、よりよいサービス提供を行う上で重要なポイントです。
業績や職場の状況にもよりますが、例えば一定のラインを超えた場合の「昇給」や従業員同士が仲良くなるような「イベントの企画」などが挙げられます。
自社内でアンケートや聞き取りを実施し、社員のモチベーションが上がる施策を検討しましょう。
5.顧客間でのコミュニティーを形成する
サービスを利用する顧客同士で交流するコミュニティー形成も重要なポイントです。
顧客同士での関わりが増えると、コミュニティー内で商品やサービスの情報を共有したり、意見交換したりするようになります。
例えば、調味料品や飲料を販売する「KAGOME」では「&KAGOME」と称し、ファン同士がコミュニケーションを取れる場を提供しています。
サービス提供側が新商品や新企画などのアクションが少なくても、顧客同士が関わりあう場を作ることで、満足度を向上させることも可能です。
顧客満足度の向上に成功した3つの事例
本章では、顧客満足度を向上させた以下の3つの事例について解説します。
- ネッツトヨタゾナ神戸株式会社
- 株式会社ヤクルト球団
- 株式会社シーネット
ぜひ、参考にしてみてください。
顧客の名前を呼ぶ電話対応で業務効率と顧客満足度が向上|ネッツトヨタゾナ神戸株式会社

ネッツトヨタゾナ神戸株式会社は、兵庫県東部エリアを中心にトヨタ車の販売・整備などを行う自動車ディーラーです。
お客様からの着信と同時に表示されるポップアップで、名前や所持している車種、過去の担当者などの情報が瞬時に分かるツールを導入し、電話対応の時間が短縮されたことに加え、顧客満足度が向上しました。
相手の情報を知り親身な電話対応が可能になったことで、お客様に安心感と信頼感を与える電話対応が可能になったからです。
また、営業スタッフも事前に要件が推測できるので、受付担当から営業担当への電話渡しがスムーズになりました。
ITシステムを導入しファンクラブ運営を黒字化|株式会社ヤクルト球団
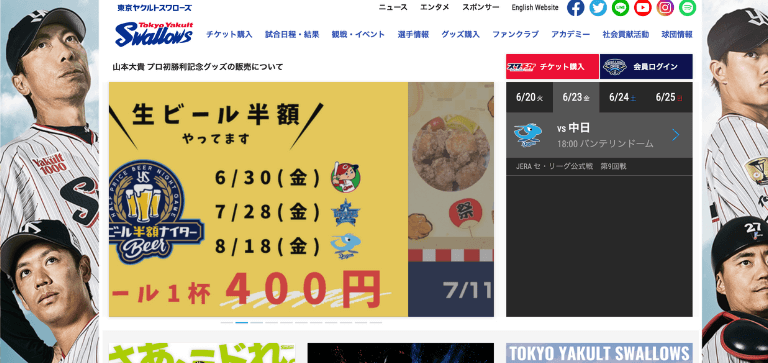
株式会社ヤクルト球団は、ファンクラブを含めたチッケティングシステムをIT化したことにより、ファンクラブ事業の黒字化に成功しました。
顧客情報やアンケート調査を定量化して分類・分析できるので仮説と検証をスムーズに行なえます。
その結果、ファンクラブの会員数が増えるだけでなく、会員のロイヤリティーを高めることに成功。ファンクラブ拡大に大きく寄与しました。
スピーディーな要件把握と電話対応ロスの軽減で的確な顧客対応が可能|株式会社シーネット
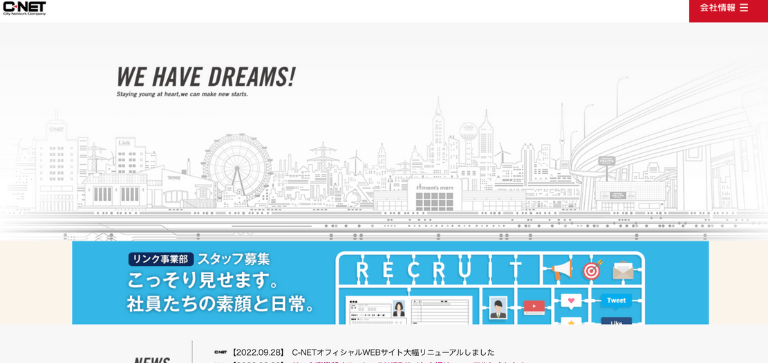
株式会社シーネットは、広告デザイン制作業やフードサービス業、リサイクルショップなど様々な事業を展開する会社です。
着信時に顧客情報が分かるツールの導入によって、早いレスポンスで顧客対応ができるようになりました。
これまでに提供したサービス内容や金額といった情報も一緒に管理されているため、電話中でもスムーズに顧客対応ができます。
スピーディーな要件把握と的確な対応が実現したことで、顧客満足度を向上できました。
参考:外出先から重要な電話に即対応 毎通話3分の保留時間を削減、通録機能により伝言ミスもゼロへ 「生産性向上」と「顧客満足度向上」効果を実感|株式会社シンカ
まずは顧客の期待を把握することから
期待を把握することで、顧客が何を求めているのかを理解し、それに対応するような製品やサービスを提供できます。
顧客満足度を向上させるに、まずは顧客の期待を把握することが重要です。
また、顧客の期待を把握することで、抱えている不満を早期に発見し、改善することも可能になります。
アンケートや口コミ調査を行い、ターゲットとなる顧客が何を期待しているのかを把握するようにしましょう。
顧客満足度と違う指標「NSP」
顧客満足度(CS)とよく似た指標にNPS(Net Promoter Score)があります。
顧客満足度は、満足度が指標であるのに対し、NSPは顧客のロイヤリティが指標になっています。
| 指標 | 内容 | |
| 顧客満足度(CS) | 満足度 | サービスに対してどの程度満足したか |
| NSP | ロイヤリティ | サービスをどれだけ推薦したいか |
NPSは、顧客のロイヤリティが指標のため、どれだけサービスを推奨したくなるかを測ります。
顧客満足度(CS)とNPSは、どちらも顧客の満足度を測定する指標として重要ですが、目的に応じて使い分けるようにしましょう。
まとめ
本記事では、顧客満足度を向上させるポイントや事例、NSPとの違いについて解説しました。
顧客満足度は企業にとってブランドイメージや売上向上にも繋がる重要な指標です。
顧客満足度は、顧客が抱く期待を上回るサービスを提供することで得ることができます。
そのためには、CRMやSFAの導入も検討していきましょう。
また、今回紹介した事例も参考にしながら、ぜひ、自社の顧客満足度を向上させるきっかけになれば幸いです。
お問い合わせはこちら
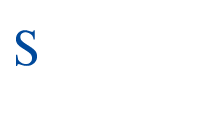 Digital Library
Digital Library 
