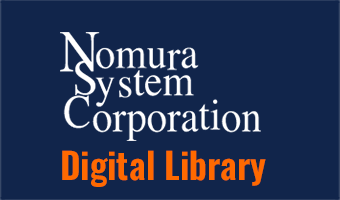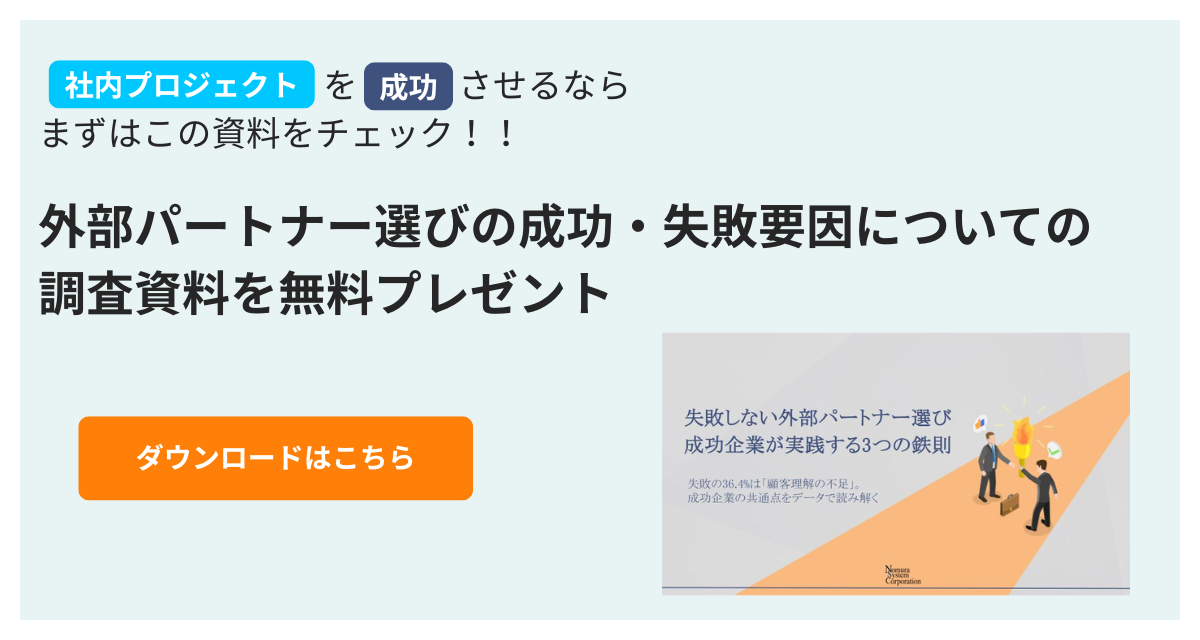DX未分類
地域DXとは?重視される理由や実践事例を踏まえて解説
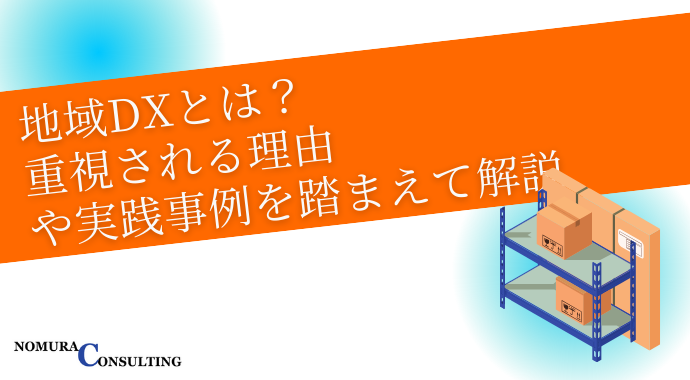
人口減少や高齢化が進む中、地域が直面する問題をデジタルの力で解決する取り組みとして地域DXが注目されています。
本記事では、地域DXの概要や重視される背景、実践事例などをわかりやすく解説します。
地域DXとは|デジタルで地域課題を解決
地域DXとは、デジタル技術を活用して地域が抱える問題に対応する取り組みを指し、総務省では「自治体DX」と「地域社会DX」の2つの視点から定義しています。ここでは、それぞれの特徴や役割について解説します.
- 自治体DXとは|行政サービスの効率化を図るデジタル改革
- 地域社会DXとは|地域の問題をデジタルで解決
参考記事:デジタルの力で社会が変わる地域DX|地域DXポータルサイト
自治体DXとは|行政サービスの効率化を図るデジタル改革
自治体DXとは、地方自治体が行政業務にデジタル技術を取り入れ、行政手続きの効率化や高度化、業務負担の軽減を図る取り組みです。紙や対面中心のアナログ業務をデジタル化し、職員や住民の双方にとって使いやすい行政サービスへの変革が期待されています。
具体的には、マイナンバーカードを活用した本人確認の電子化や、各種証明書のオンライン交付、申請手続きのデジタル化などが挙げられます。こうした取り組みは、単なるITツールの導入にとどまらず、業務プロセスそのものを見直し、住民の利便性向上を重視する点が特徴です。
地域社会DXとは|地域の問題をデジタルで解決
地域社会DXとは、行政だけでなく、住民や地元企業、医療・教育機関など地域全体が連携し、デジタル技術を活用して課題解決に取り組むことです。
人口減少や高齢化、交通・農業の人手不足といった社会的な問題に対し、テクノロジーを用いて生活の質を高め、地域の持続可能性を確保することが目的です。
たとえば、スマート農業の導入やデータ活用による高齢者の見守りシステムなどが挙げられます。また、公共交通の維持に向けた自動運転の導入実証を進める自治体も増えてきました。こうした自治体DXを土台とした地域社会DXの施策は、行政と地域社会が一体となって進める包括的かつ実践的な変革であり、地域の未来を支える不可欠な要素といえます。
地域DXが重視される理由|地域の持続可能性を確保するため
デジタル技術を活用して地域の問題を解決する地域DXは、地域社会の持続可能性を左右する重要な取り組みです。
近年、日本では人口の減少や少子高齢化の進行など、将来的に深刻化が予想される社会的な問題に直面しています。地域によっては、医療・福祉・教育・交通など暮らしを支えるサービスの維持が困難になるケースもあるでしょう。
このような状況を踏まえ、行政サービスの効率化だけでなく、地域産業や暮らし全体を見直す本質的な変革が求められています。たとえば、業務のデジタル化やデータ活用は、多くの自治体で導入が進められている代表的な施策です。
地域DXは、省力化やコスト削減にとどまらず、地域の未来を再設計するための実践的なアプローチとして重要な取り組みといえます。
地域DX実現に向けた主な課題
地域DXを実現するには、さまざまな課題への対応が欠かせません。ここでは、主な課題を3つ解説します。
- 地域DXを支える人材の確保と育成
- 住民の理解促進と不安の解消
- 導入・運用・維持にかかる財源の確保
地域DXを支える人材の確保と育成
DXを担う人材の不足は、多くの自治体が抱える問題のひとつです。DX推進を担う専門的な人材が圧倒的に不足しているほか、配属された担当者のITリテラシーや理解度にも差が生じ、現場での対応にばらつきが生じるケースも少なくありません。
地域DXをスムーズに進めるには、研修やOJT(職場内訓練)を通して地域課題やデータ活用に関する理解を深めてもらうことが大切です。DXを一部の人材や組織に依存せず、地域全体として取り組む姿勢が求められます。
住民の理解促進と不安の解消
地域DXを円滑に進めるには、ITに対して苦手意識を持つ住民の理解や共感を得ることが必要です。とくに、高齢化が深刻な地域では、デジタルに不慣れな層に配慮した設計や情報提供を重視する必要があります。
システムやサービスを導入する際は、利便性だけでなく使いやすさも意識するとよいでしょう。また、疑問や悩みを抱えた住民が相談しやすいサポート体制の構築も、地域DXの定着と促進に役立ちます。
導入・運用・維持にかかる財源の確保
地域DXの導入には、システム構築の初期費用、運用や維持管理に関するコストも発生します。財政に余裕のない小規模自治体や過疎地域では、国や都道府県の補助金に頼らざるを得ない状況も多く、補助終了後に事業継続が難しくなる場合もあります。
持続可能な地域DX推進に向けて、費用対効果をおさえることが大切です。たとえば、市区町村単位ではなく県単位でサービスや体制構築を横展開することが、コストを抑えられます。財源負担を抑えながら、効果的に投資するための設計が地域DX成功のポイントです。
地域DXに成功した事例
ここでは、地域DXを導入して成功した事例を2つ紹介します。
- 北海道岩見沢市|300名の生産者が参加するスマート農業の先進自治体
- 群馬県前橋市|高齢化対策にバスの自動運転実証を開始
北海道岩見沢市|300名の生産者が参加するスマート農業の先進自治体
北海道岩見沢市では、2005年に1,580戸あった農家が2023年には786戸まで減少し、そのうちの6割が後継者不在という問題を抱えていました。この状況を受けて設立した組織が「いわみざわ地域ICT(GNSS等)農業利活用研究会」です。
同研究会は、地域の農業課題をICTで解決する実践型の組織として活動を開始しました。たとえば、GNSS(全地球航法衛星システム)による位置情報配信サービスを活用した農機の自動操舵技術や、気象データをもとにした収穫時期の予測など、先端的な技術導入を進めています。
こうした取り組みは、北海道大学や民間事業者と連携した産学官連携により支えられ、現在ではおよそ300名の農業従事者が参加する施策に成長しました。スマート農業の先進地域として全国的にも注目される事例です。
参考記事:-地域DXの実現へー9つの好事例と成功の秘訣インタビュー編 令和5年4月版|総務省
群馬県前橋市|高齢化対策にバスの自動運転実証を開始
群馬県前橋市では、マイカー依存に伴う高齢者の運転事故や公共交通衰退、バス運転手の不足などが問題となっていました。
こうした中で、地域DXの一環として、自動運転バスによる移動支援の実証実験を開始しました。プロジェクトは、大学や企業の協力を得ながら推進されたほか、利用者である地域住民の声も反映された点が大きな特徴です。
実験は段階的に進められ、自動運転の技術は着実に向上しています。テスト走行を重ねた結果、現在では、運転手が乗車せずに走行可能な「自動運転レベル4」の水準に達しました。2025年度には、市内の一部公道において実用化される見通しであり、正式な国の認可申請も予定されています。
参考記事:-地域DXの実現へー9つの好事例と成功の秘訣インタビュー編 令和5年4月版|総務省
地域DXは行政と地域社会の連携で実現する取り組み
地域DXとは「自治体DX(行政のデジタル化)」と「地域社会DX(民間や地域全体のデジタル活用)」の両輪で成り立つ取り組みです。どちらか一方ではなく、行政と地域社会が連携して相互にデジタル化を進めることが求められます。
地域DXの導入に悩んでいる方は、DXコンサルティングの活用がおすすめです。ノムラシステムでは、地域の課題や現状を踏まえた持続可能な取り組みのサポートを提供します。お気軽にご相談ください。
東京MXの番組で、ノムラシステムコーポレーションが取り上げられました。詳しい内容を知りたい方は、ぜひ下記のYouTube動画をご覧ください。
ノムラシステムコーポレーションの紹介動画
お問い合わせはこちら