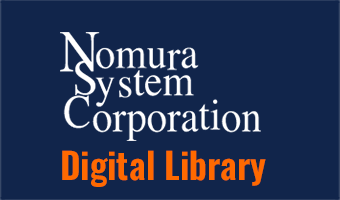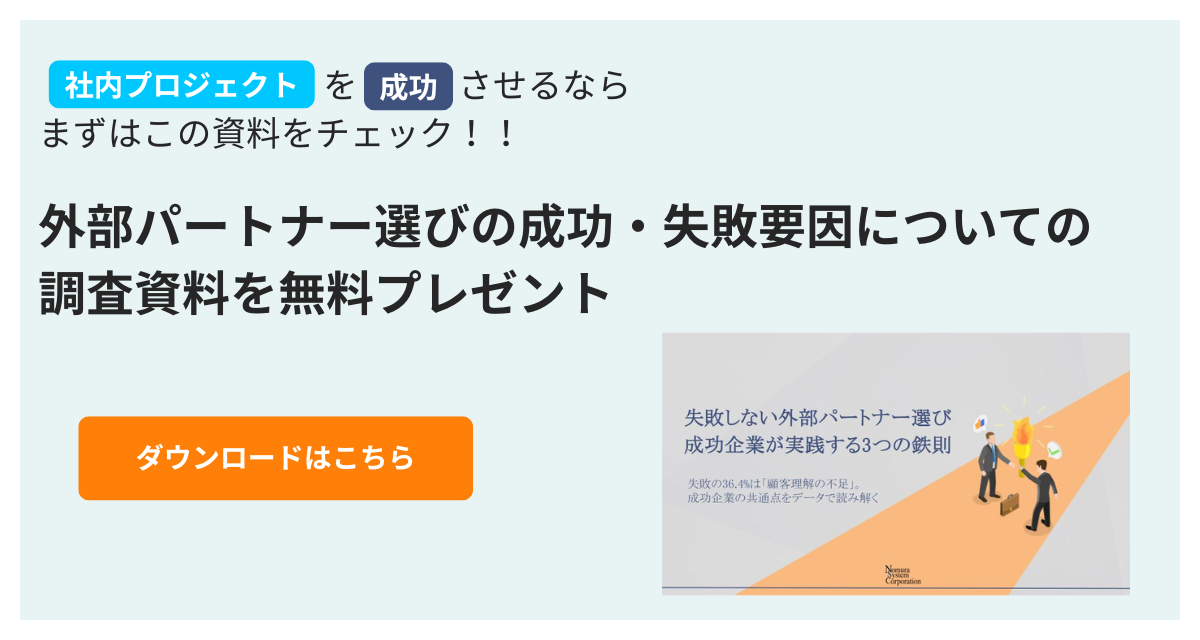DX
製造業における人手不足とは?現状・原因から対策・事例まで徹底解説

現代の製造業企業の多くは、深刻な人手不足に直面している状況です。このまま放置すれば、企業存続にかかわる問題が現実となるでしょう。しかし、適切な対策を講じることで、この問題は解決可能です。
当記事では、製造業の人手不足の現状から根本原因までを詳しく分析し、実効性の高い解決策を具体的な企業事例とともに紹介します。ぜひ参考にしてください。
製造業では約11万人の人材が不足
製造業の人手不足は統計データで明確に示されており、深刻な労働力不足が継続しています。
経済産業省によると、製造業の労働人口は2002年~2021年までの約20年間で、1,202万人から1,045万人へと約157万人減少しました。その結果、約11万人の需給ギャップが生じていると示されており、労働人口の減少傾向は依然として深刻な状況です。
特に深刻なのは労働者の年齢構成の変化です。34歳以下の若年労働者が大幅に減少する一方で、高齢労働者数が増加しており、人材のバランスが大きく崩れています。
また、製造業における女性労働者の割合は他産業と比較して低く、人材の多様化による労働力確保の観点からも改善が求められています。
労働力不足を解消するには、若手人材の確保と女性活躍推進の両面からアプローチが必要といえるでしょう。
参考:2022年版ものづくり白書|経済産業省
参考:2023年版ものづくり白書|経済産業省
人手不足が製造業に与える影響
製造業の人手不足は以下のようにさまざまな影響を及ぼし、企業の競争力を喪失するリスクとなります。
- 生産性低下による納期遅延や品質維持の困難
- 顧客満足度低下による失注や競争力の低下
- 熟練技術継承の断絶
最も深刻な影響は熟練技術継承の断絶です。ベテラン労働者の引退により長年培われた製造ノウハウが失われ、企業の存続に関わる重大な問題となっています。
このような問題に対処するため、多くの企業がDX・リカレント教育・リスキリングを推進しており、人手不足時代を乗り越える経営モデル構築を目指しています。
関連記事:DXが生産性向上に有効な理由とは?事例を踏まえて解説
製造業の人手不足が進行する理由
製造業の人手不足が進行する理由は、以下のような複数の要因が重なっているためです。
- 少子高齢化の影響と若者離れ
- ネガティブな職場イメージが人手不足を加速
- 他業界と比べて給与や待遇が悪い
それぞれの要因を整理して見ていきましょう。
少子高齢化の影響と若者離れ
少子高齢化によって働き手が減る中、各業界で人材の奪い合いが激しくなっています。特に製造業では、人材確保が一段と厳しい状況に置かれています。
「2022年版ものづくり白書」によると、若者離れと人材流出が顕著であることが見て取れます。主な傾向は以下の通りです。
- 製造業の就業者数は約157万人減少
20年間で労働人口が大幅に減少し、業界全体の人手不足が進行しています。 - 34歳以下の若年就業者は約384万人から約263万人へ、約121万人減少
若年層の減少が著しく、技能継承や将来の担い手不足が深刻化しています。 - 全産業に占める製造業の就業割合は19.0%から15.6%へ低下
産業全体における製造業の存在感が縮小し、人材獲得競争で不利な立場に置かれています。
労働力不足の深刻さは求人倍率にも表れており、2023年1月時点の職種別有効求人倍率では、以下のように非常に高い水準を記録しています。
- 生産工程の職業:2.00倍
- 機械整備・修理の職業:4.38倍
- 金属材料製造の職業:3.32倍
少子高齢化の影響は今後加速することは確実であるため、製造業企業はいかに若年層を中心に人材を確保していくかが重要となるでしょう。
参考:一般職業紹介状況(パート含む)|厚生労働省
ネガティブな職場イメージが人手不足を加速
製造業は、3K(きつい・汚い・危険)というネガティブイメージが定着しており、人手不足を深刻化させています。
また、指導者不足により十分な指導を受けられず、技術習得や職場適応に困難を抱えるケースが増えているのも人手不足の要因です。
このように、製造業はマイナスイメージばかりが先行しているため、業界全体でのイメージ向上と実際の労働環境改善が急務となっています。
他業界と比べて給与や待遇が悪い
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査(2023年)」によると、製造業の平均賃金は約306.0千円で、他産業と比較してやや低い水準です。高水準である情報通信業(約38.12万円)や金融・保険業(約39.34万円)との賃金差は7万円以上にも及びます。
賃金差に加えて、将来的な賃金上昇や福利厚生の内容においても、製造業は他業界より見劣りする傾向があります。そのため、給与や福利厚生が充実していない製造業は他業界と比べて人気が低く、人材流出を招きやすい状況です。
業界が持続的に発展するには、技術力向上や生産性向上による付加価値創出と、それに見合った適正な賃金設定が必須です。
参考:令和5年賃金構造基本統計調査 結果の概況(産業別)|厚生労働省
製造業の人手不足に対しての解決策
製造業の人手不足に対しては、すでに多くの企業や政府が具体的な対策を講じています。
- 製造業の人手不足解決策
- 自動化・AI技術の導入
- 若者の製造業離れ対策
- 労働環境の改善
- 政府・自治体の支援と政策活用
上記対策の詳細をそれぞれ解説します。
自動化・AI技術の導入
製造業における自動化およびAIの導入は、人手不足解決の手段として注目されています。以下は、その具体的な活用例です。
- 生産ラインへのロボット導入やAI活用
製造現場の作業負担軽減と生産性向上を実現できる。 - AIによる外観検査や異常検知
工程の最適化による品質向上、人手によるミスを減らす効果が期待できる。
作業の自動化には初期投資コストがかかるものの、長期的には労働力不足の解消や生産効率の向上を図ることが可能です。
導入にあたっては、初期投資の妥当性を検討すること、技術と人材のバランスを取りながら活用することがポイントとなります。
関連記事:DX市場規模が拡大する理由とは?国内外の動向を踏まえて解説
若者の製造業離れ対策
若者の製造業離れは深刻な課題ですが、公的プログラムや企業独自の取り組みが効果を上げています。主な対策は以下の通りです。
- 公的なキャリア支援の推進
厚生労働省は高校・専門学校・大学と連携し、若年層向け製造業キャリア支援プログラムを展開。製造業の魅力を伝える取り組みを強化しています。 - 企業による人材教育と研修の充実
製造業企業では、インターンシップ・職業訓練・若手研修プログラムを充実させ、技術継承・若手の早期戦力化・人材定着を目指しています。
このような公的プログラムと企業の取り組みの相乗効果により、若者の製造業離れは徐々に緩和されつつあり、人材確保や戦力化に実績が見え始めています。
特にキャリア支援と実務体験の両面からのアプローチが効果的とされており、若者が製造業の将来性や働きがいを実感できる環境づくりが重要となっています。
労働環境の改善
製造業は、他業種よりも労働環境の問題が懸念される業種です。大手をはじめとした製造業企業では、以下のような労働環境改善に積極的に取り組み、従業員満足度向上を通じた人材確保を進めています。
- 健康管理制度やメンタルヘルスケアの導入
- 製造業特有のストレス要因への対応
- 残業時間の厳守などの労働条件見直し
- フレックスタイム制やリモートワークといった柔軟な働き方の推進
具体的な成果を挙げている企業の事例として、以下が確認できます。
- Jマテ.カッパープロダクツ株式会社
RPA・AI・IoTを導入して紙作業や目視検査を削減し、現場の負担を大幅に軽減。年間4,000時間の業務削減と生産性37%向上を実現し、従業員の働きやすさにつなげました。 - 疋田産業株式会社
集金や手形処理などの間接業務を自動化・電子化し、社員の事務負荷を削減。創出した余力を顧客支援に活用することで、2023年度に売上高5.98%増を達成し、働きやすい環境を確立しました。
働きやすい環境づくりによる社員の定着率向上は、人手不足解消の重要な要素です。
関連記事:製造業向けERPとは?導入するメリットやMESとの連携について解説
製造業における人手不足解消の助成金制度や職業訓練支援プログラムについて
政府は製造業の人手不足解消に向けて多様な支援制度を展開しています。例えば、中小企業向けの代表的な支援には、以下が挙げられます。
- 厚生労働省「人材開発支援助成金」
職業訓練実施企業に対し訓練経費や賃金の一部を助成。 - 厚生労働省「中小企業リスキリング支援事業」
研修・職業訓練実施企業を支援。 - 文部科学省の留学生受入施策
留学生の日本での就職支援やキャリア教育を充実させ、国際人材の活用を推進。
上記支援は製造業企業の人材確保に大きな効果を持っています。
また、以下のような製造業のDX推進支援も提供されています。
- 経済産業省「中小企業省力化投資補助金」
IoT・ロボット導入による人手不足解消を支援。 - 「中堅・中小企業の賃上げ・成長投資補助金」
設備投資による成長促進を支援。
上記を活用したデジタル技術の導入、スマートファクトリー化は、生産効率化と人手不足の解消が期待されています。
製造業企業が人手不足の問題を解決した事例
ここでは、製造業企業が人手不足へ対応した事例を解説します。
- Jマテ.カッパープロダクツ株式会社|業務自動化と見える化による人手不足対応
- 疋田産業株式会社|社内外DXで省力化を進め、人手不足に対応
実際に成果を上げている企業の事例から学ぶことは重要ですので、参考にしてください。
Jマテ.カッパープロダクツ株式会社|業務自動化と見える化による人手不足対応
Jマテ.カッパープロダクツ株式会社は、RPA・AI・IoTを活用したDXにより人手不足の対策をしています。
当時、同社が抱えていた問題は、地方における生産年齢人口の減少に起因する、紙ベース処理・目視検査・現場巡回といった業務の逼迫です。約30年で人口3割減の予測もあり、早急な対策が必要でした。
解決策として取り組んだDX施策は以下の通りです。
- RPAで日常業務を自動化し、AIによる製造プロセスの不良検出を導入
- IoTと見える化でラインの異常検出・トラブル可視化を推進
- ノーコード・ローコードを用いた現場主導の改善
結果として、2024年9月時点で年間4,000時間の業務削減と生産性37%向上を達成しました。
疋田産業株式会社|社内外DXで省力化を進め人手不足に対応
疋田産業株式会社は、社内業務自動化で創出した人員余力を取引先への省力化提案に活用し、人手不足下でも成長を維持する運営モデルを確立しています。
同社では工数逼迫により多くの社員が多忙となり、紙ベース手続きや集金・手形処理など人手依存の間接業務が負荷となっていました。
解決策として、以下の取り組みを実施しました。
- SFA導入によるデータ起点の営業体制構築
- AI-OCRとRPAによる定型処理自動化
- 集金から振込、手形から電子記録債権への切り替え
結果、2023年度売上高5.98%増を達成し、事務負荷軽減を実現しています。創出した余力を顧客支援に振り向け、限られた人員でも売上向上につなげる好循環を実現しました。
参考:【事例】自動化、効率化、そして新たな付加価値の提供へ|デジタル事例データベース
これからの製造業に求められる人手不足への取り組み
製造業の人手不足は深刻な問題ですが、適切な対策により乗り越えられる問題です。自動化・AI技術の導入、労働環境の改善、政府支援制度の活用といった多角的なアプローチにより、限られた人員でも高い生産性を実現できます。
ノムラシステムは、製造業の人手不足へ対応したDXコンサルティングならびにDXソリューションの提供を行っています。人手不足でお悩みの製造業企業の方は、お気軽にご相談ください。
東京MXの番組で、ノムラシステムコーポレーションが取り上げられました。詳しい内容を知りたい方は、ぜひ下記のYouTube動画をご覧ください。
ノムラシステムコーポレーションの紹介動画
お問い合わせはこちら