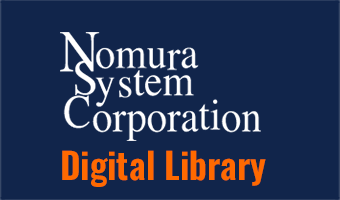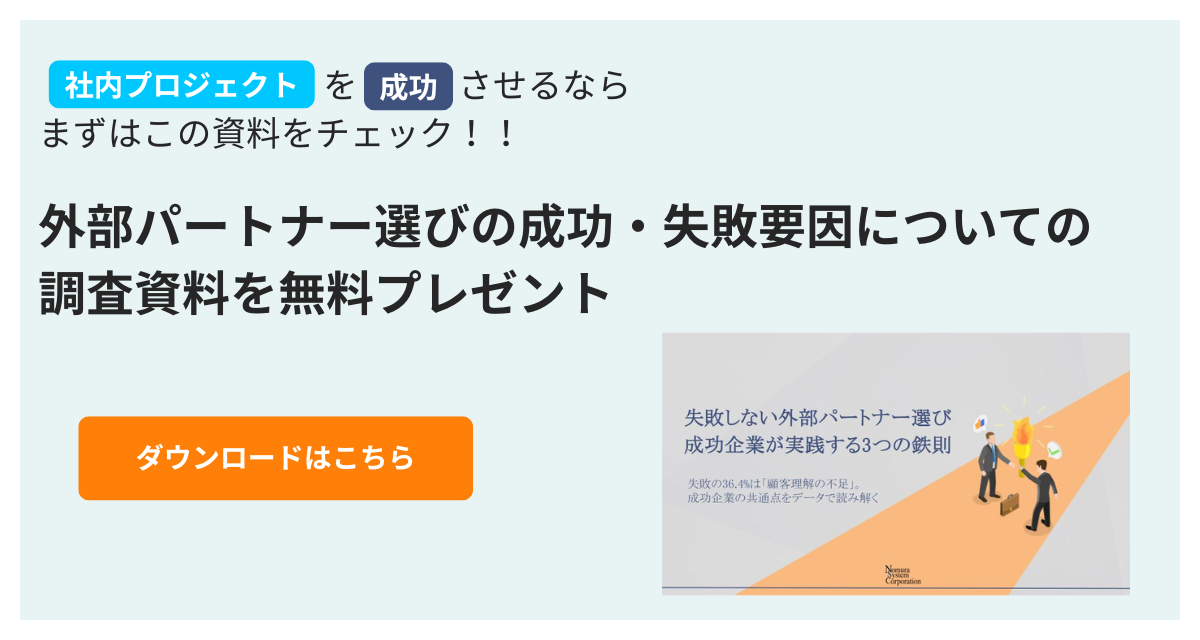コンサルタント記事
クリーンコアを実践するために。現状把握と目的共有がもたらす成功の条件とは?

- 話者:飯田 悠紀
- PMO戦略部/PMOコンサルティング事業部 執行役員
クラウド移行やグローバル展開の加速に伴い、ERPの運用において「クリーンコア思想」が強く求められるようになってきました。アドオンやカスタマイズを避け、標準機能を活用するというこの考え方は、一見するとシンプルですが、実際のプロジェクト現場で定着させるのは容易ではありません。
本稿では、クリーンコアをどう運用し、どう定着させていくかを説明します。現状把握から目的共有、そしてチェンジマネジメントに至るまで、現場で直面する課題とその乗り越え方を整理し、DX推進における指針を提示できればと思います。
クリーンコア思想が求められる背景には、全体最適の考え方がある
近年、SAPを中心としたERP運用において「クリーンコア思想」が注目を集めています。
クリーンコア運用とは、SAPが提唱する戦略で、ERPシステムのコア部分をできるだけカスタマイズせず標準機能(Fit to Standard)を活用し、その外部に差別化や拡張機能(アドオン)を開発することで、システムの拡張性・保守性を高める運用方式のことです。
つまり、アドオンやカスタマイズを極力避け、標準機能を活用して業務を進めるという考え方です。
背景にはいくつかの要因があります。
まず、クラウド移行の加速です。従来型のオンプレミスERPでは自社固有のカスタマイズが可能でしたが、クラウド環境では頻繁なアップデートに追随する必要があり、カスタマイズが足かせになるケースが増えています。
次に、グローバルでの統一志向です。海外拠点を含む多国籍企業では、業務プロセスを標準化しなければ運用効率が下がり、全体最適が損なわれます。こうした理由から「標準に寄せる」動きが強まっているのです。
日本の強みは「属人的な工夫」や「小回りの利く現場対応」であり、各部署がそれぞれ最適化して業務を回してきた歴史があります。
しかし、そのやり方はグローバルに展開する際や経営全体の効率化を目指す際に足かせとなることもあります。
当社では、トップダウンでプロセスを統一する仕組みが不可欠であり、その思想を支えるのがクリーンコアであると考えています。
クリーンコア思想の運用のポイントは現状把握。ここは変わらない。
クリーンコア思想のもとでERPを運用する際には「導入 → 運用 → アップデート → 定着」というサイクルが基本となります。この流れはクラウド環境に適応するために不可欠とされています。
まず導入段階では、システムの標準機能を前提にプロセスを設計します。ここで大切なのは、業務の「現状把握」を徹底することです。
Fit Gap方式でも、Fit to Standardでも、結局コア部分は変わりません。どちらの方式を選ぶにしても、現場の業務を丁寧に棚卸ししなければ、後々業務との大きなギャップが生まれ、適切に運用できないと言った問題が発生してしまいます。
また、運用段階では、アップデートに迅速に追随する体制を整える必要があります。クラウドERPは半年や一年ごとにアップデートが入るケースが多く、従来のオンプレミスのように数年ごとに大規模改修する発想とは異なります。
そして定着フェーズで重要になるのが「目的の共有」です。
目的が曖昧なままでは、ユーザーはなぜ標準化に合わせなければならないのか納得できません。逆に、経営全体の最適化という目的が共有されていれば、現場も負担を受け入れやすくなります。
このように、クリーンコア運用を成功させるには、単なるシステム導入にとどまらず、現状把握の徹底と目的意識の共有が一貫して求められます。
クリーンコアはシンプルだが、目的を明確にしないと難しい
クリーンコアは、シンプルで理にかなった考え方ですが、実際に運用してみるといくつかの難しさがあります。
まず、プロジェクトの目的が時間の経過とともにずれてしまう点です。導入当初は「標準に寄せる」という方針で始めても、現場からの要望や担当者の交代が重なると目的が曖昧になりがちです。
Fit GapであってもFit to Standardであっても、現状把握を丁寧に行うことが欠かせないのはそのためです。
次に、現場の負担感です。標準プロセスに合わせるということは、これまで慣れ親しんだ手順を変えることを意味します。経営視点では合理化であっても、現場からすれば「負担が増えた」と感じられることが少なくありません。こうした温度差は、システム活用の障害になる可能性があります。
さらに、体制面の問題もあります。プロジェクトはピラミッド型で構成されることが多いですが、一部に経験の浅いメンバーが入ると、その部分から品質が崩れ、全体に影響が及びます。
標準に寄せる難易度が高いのは、この「弱い部分が全体を左右してしまう構造」にも要因があると感じています。
クリーンコアの思想はシンプルですが、実際の現場では「目的の共有」「現場との折り合い」「体制の維持」といった複合的な課題を乗り越える必要があるのです。
クリーンコアを成功させるためにはチェンジマネジメントも不可欠
クリーンコアの思想を掲げても、現場で運用していくのは決して簡単ではありません。どうしても「従来のやり方を変えたくない」という声が上がりますし、短期的な利便性を優先すれば、気づかないうちに個別改修やアドオンに流れてしまいます。しかしそれでは、クラウド移行やグローバル標準化の利点を十分に享受できません。
大切なのは、まずプロジェクト全体で目的を正しく共有することです。Fit-GapであってもFit to Standardであっても、現状を把握するプロセスは欠かせません。そのうえで、標準に合わせる部分とそうでない部分を明確にしていく。この区分を曖昧にすると、最終的に「何のためのクリーンコアか」がぼやけてしまうのです。
また、チェンジマネジメントも不可欠です。標準に寄せるということは、現場の「当たり前」を変えることを意味します。経営層が掲げる全体最適の課題感と、現場が理解し納得できる理由をつなぎ、なぜ変化が必要なのかを丁寧に説明して浸透させる必要があります。
結局のところ、クリーンコアを運用するというのはシステムだけの話ではありません。企業として「何を解決したいのか」を徹底的に共有し、そのために必要な変化を受け入れる文化を育てられるかどうか。そこに成功の条件があると考えています。
クリーンコアは「思想」から「実践」へ
クリーンコアは単なる技術上の選択肢ではなく、企業がこれからのDXを進めるうえで避けて通れない思想だと言えます。標準機能を活用し、複雑なカスタマイズを避けることで、クラウド移行やグローバル標準化といった大きな経営課題に応える基盤が整います。
しかし実際の現場では、従来のやり方を変えることに抵抗が生まれ、短期的な利便性を求めてアドオンに流れてしまう危険もあります。だからこそ、プロジェクト全体で目的を共有すること、そしてチェンジマネジメントを徹底することが成功の鍵になります。
クリーンコアを「アドオンをしない」という表面的なルールと捉えずに、企業として「何を解決したいのか」を全員で理解し合う仕組みだと考えることが重要です。
標準化を通じて業務の在り方を見直し、全体最適へと舵を切る。この思想を浸透させることが、結果的にシステムを超えた企業変革につながっていきます。