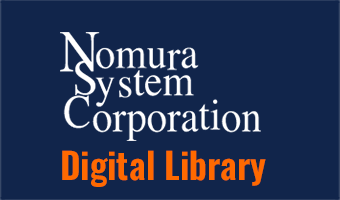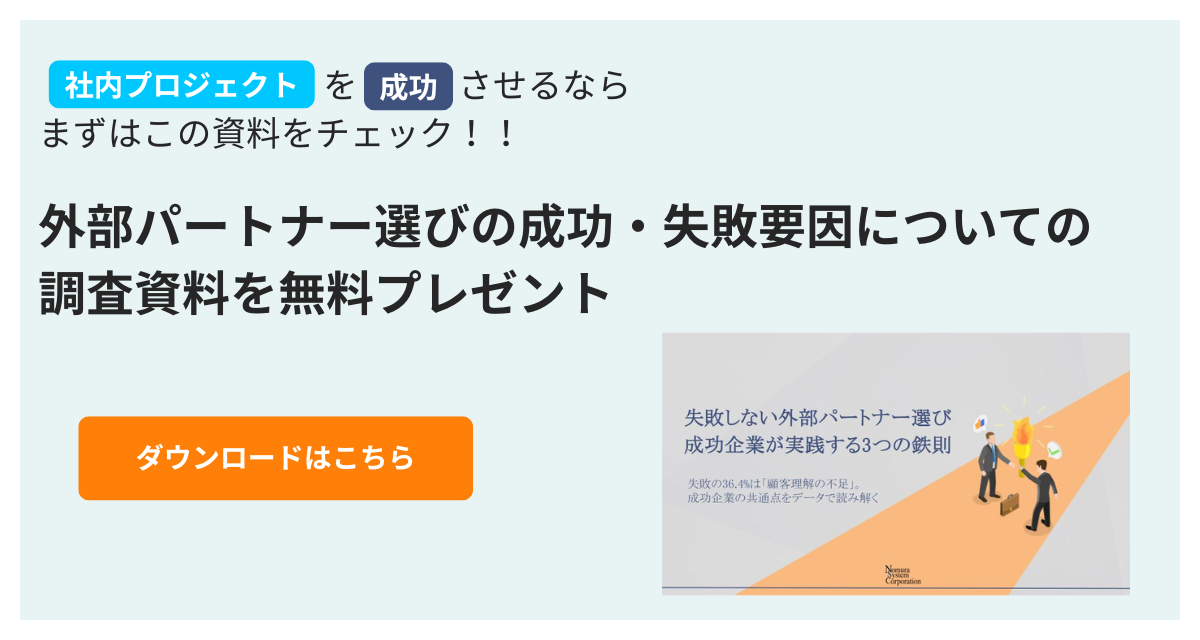DX
経済産業省のDXレポートとは?2018年版〜最新版2.2の概要を解説
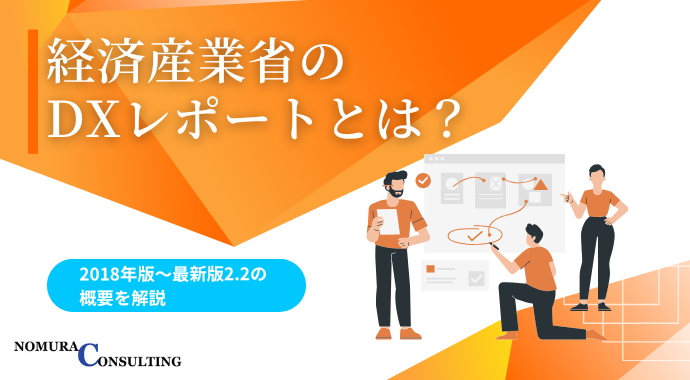
DXレポートは、経済産業省が公表するDX(デジタルトランスフォーメーション)に関する現状や課題、推進に向けた方向性をまとめた報告書です。
本記事では、DXレポートのこれまでの流れを整理するとともに「DXレポート2.2」が提言する3つのアクションもわかりやすく解説します。
DXレポートとは|経済産業省によるDXの現状や課題をまとめた報告書
DXレポートは、DXを実現するために必要な課題を整理し、企業が取るべき対応策を提言した経済産業省による報告書です。
企業の成長を妨げる老朽化・複雑化したITシステム(レガシーシステム)の問題や、DX推進を阻む要因が明確にされています。
また、企業の取り組み状況を整理して、変革に向けた具体的な指針も示されました。
2018年に初版として「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開〜」が発表されて以降、社会の変化を踏まえながら継続的に内容が見直されています。
DXレポートは、日本全体がデジタル変革を進めるための方向性を示す重要な指針といえるでしょう。
DXレポートで言及された「2025年の崖」とは
2018年のDXレポートで登場した「2025年の崖」とは、2025年以降、企業の競争力や経済全体に大きな損失をもたらすとされるリスクのことです。
具体的には、人材面(デジタル人材の不足)や技術面(レガシーシステム化の進行)などにより、企業のDX化が阻害される懸念が言及されています。
2025年の崖の詳しい意味や問題点、企業がとるべきとされる対策については以下の記事でも解説しているため、あわせてご覧ください。
関連記事:「2025年の崖」とは?
2018年DXレポートその後の流れ
2018年9月に公表された初版のDXレポートは、「2025年の崖」を背景に老朽化したシステム刷新の必要性等が強調され、危機感の喚起が中心でした。
以降も内容を発展させながら、継続して次のように発表されています。
- 2018年|DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~
- 2020年|DXレポート2(中間取りまとめ)
- 2021年|DXレポート2.1
- 2022年|DXレポート2.2
DXレポート2(中間取りまとめ)
2020年12月に公表されたDXレポート2(中間取りまとめ)では、DXの本質はレガシー企業文化からの脱却であるという認識が示されました。
そのうえで、経営者主導の推進や社内体制の確立などの必要性も強調されています。
背景のひとつには、2020年初頭から猛威を振るった新型コロナウイルス感染症の拡大があります。
これを機に社会全体のデジタル需要が急速に高まり、ITインフラの整備状況をはじめとするDX対応力の格差が顕在化しました。
さらに、2018年のDXレポートにより、「DX=レガシーシステム(既存ITシステムの老朽化)の刷新」という本質を外れた理解が広まり、取り組み自体が不十分だったことも当時の課題とされています。
そこでDXレポート2では、DX推進においては単なるシステム刷新にとどまらず、企業文化や組織そのものを変革することの必要性が示されました。
DXレポート2.1
2021年8月公表のDXレポート2.1では、DXレポート2の補完として、ユーザー企業とベンダー企業の「相互依存関係」の脱却やデジタル産業創出の必要性を強調しました。
IT対応をベンダー任せにする一方で、ベンダー側も労働力に応じた価格設定でリスク回避する相互依存の構図を「低位安定」とし、デジタル産業構造への変革を阻む要因として指摘されています。
この低位安定な関係から脱するには、ユーザー企業とベンダー企業という区別を無くし、各企業が自発的にデジタルケイパビリティ(デジタル技術を活用する能力)を磨くことが重要です。
以上をはじめとして、DXレポート2.1ではデジタル産業の重要性とその役割、企業間の相互依存関係の脱却やデジタル技術を活用した価値創出の重要性について提示されています。
参考:経済産業省「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」
DXレポート2.2
執筆時点で最新版となる2022年公表のDXレポート2.2では、デジタル産業への転換に向けた具体的なステップと行動指針が提示されています。
近年、DXの重要性は徐々に浸透しつつある一方で、DXレポート2.1で課題とされたユーザー企業とベンダー企業の相互依存構造は解消されていません。
DXの本格的な推進には、業種・企業の垣根を越えた産業全体の変革が必要であり、社会全体での取り組みが求められます。
そこでDXレポート2.2では、デジタル産業への転換を成功に導く共通指針として3つのアクションが提起されました。
各アクションの具体的な内容については次項で解説します。
DXレポート2.2が提示する3つのアクション
DXレポート2.2では、企業に向けて、デジタル産業化を進めるべく、以下3点のアクションが提示されました。
- デジタルを、省力化・効率化ではなく、収益向上にこそ活用すべきであること
- DX推進にあたって、経営者はビジョンや戦略だけではなく、「行動指針」を示すこと
- 個社単独ではDX推進が困難であるため、経営者自らの「価値観」を外部へ発信し、同じ価値観を持つ同志を集めて、互いに変革を推進する新たな関係を構築すること
収益向上のためにデジタル技術を使いこなす
DXレポート2.2では、DX推進に成功している企業の特徴として、収益向上に直結するデジタル活用の実践が挙げられています。
DXの本来の目的は、新たな価値を創出し、持続的な企業成長を実現することです。
しかし現状では、効率化・省力化にデジタル投資するケースが多く、DXの本質にまで踏み込めていない企業も少なくありません。
DXで収益向上を目指すには、デジタル技術を活用して新たなビジネスを創出したり、既存ビジネスの付加価値を高めたりする必要があります。
ビジョンだけでなく行動指針まで示す
DX推進がうまくいく企業の傾向として、経営層が行動指針を明示し、組織全体に方向性を共有している点が挙げられます。
ビジョンの提示も重要ですが、それだけでは現場レベルでDXに向けた具体的な行動が落とし込めず、従業員も自らの行動をイメージしにくいでしょう。
社内の一体感を深めるには、実践的な方向性の共有も不可欠です。
経営陣がDX推進の方向性とあわせて「どのように行動すべきか」を示すことで、従業員一人ひとりがDX実現に向けて行動しやすくなります。
CEO・CDO・CIOといった経営層が具体的な行動指針を提示することでデジタル変革が後押しされる可能性は、DXレポート2.2でも指摘されています。
関連記事:DXを進める組織は変革が不可欠!類型や必要な機能、事例を紹介
同じ価値観を持つ同志を集める
DXレポート2.1では、ユーザー企業とベンダー企業の垣根を越えて、共に価値を創出し、持続的な成長を目指す関係性の構築が重要であると指摘されました。
さらにDXレポート2.2では、従来の効率性を重視した低位安定な取引関係に代わり、収益向上を共通の目的として、互いに高め合う「共創関係」の構築を提示しています。
また、自社だけで完結するのではなく、他社を牽引しながら産業全体を変革していく姿勢もDXレポートで重視されているポイントです。
こうした価値観の共有は、企業間の協働をより強固にし、DXを進めるうえで不可欠な要素といえます。
DXレポートを踏まえてデジタル変革を進めよう
DXレポートは、DXの課題を整理し実現に向けた提言をまとめた報告書です。
2018年の初版に続き、DXレポート2、追補版2.1、2.2と展開されています。
とくに、DXレポート2.2は、DXの本質につながる重要な指針です。
DXが進まず、デジタルを活用した効率化にとどまっている場合は、一読してみるとよいでしょう。
DXレポートをきっかけにDX推進に興味を持たれた方は、コンサルティングの利用がおすすめです。
ノムラシステムでは、DXコンサルティングサービスを提供しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
東京MXの番組で、ノムラシステムコーポレーションが取り上げられました。詳しい内容を知りたい方は、ぜひ下記のYouTube動画をご覧ください。
ノムラシステムコーポレーションの紹介動画
お問い合わせはこちら