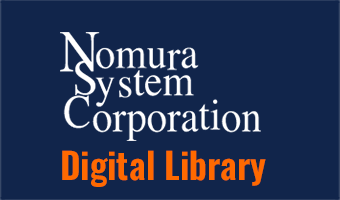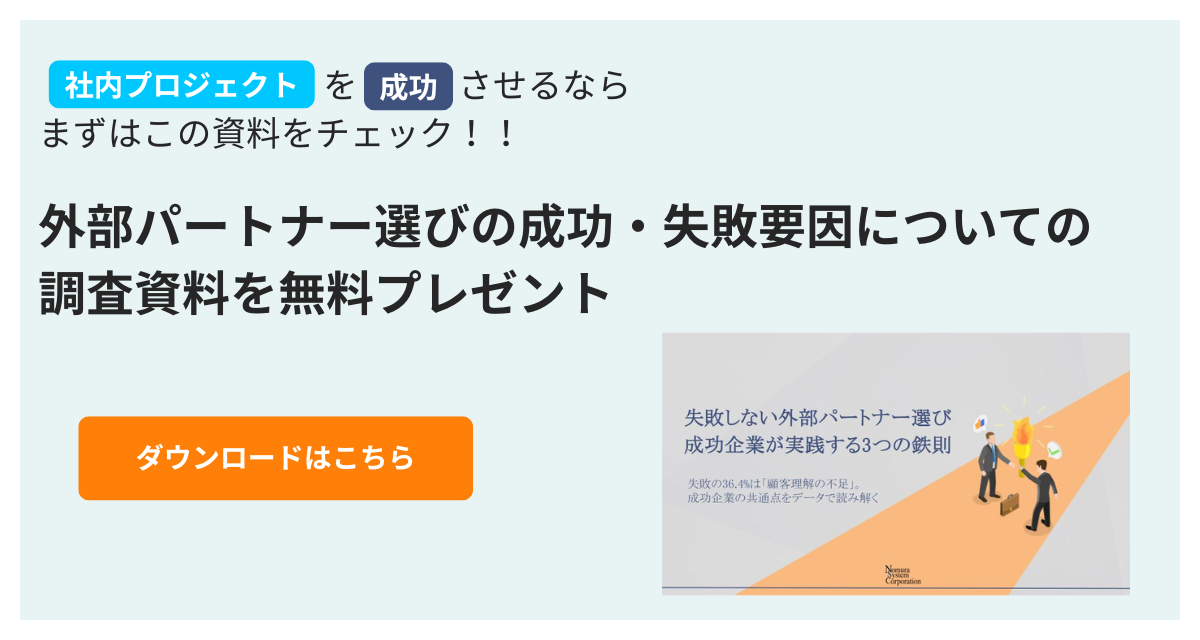コンサルタント記事
販売管理(SD)モジュールで解決できる複雑性と15年前のSAP刷新の課題|DXの現場

- 話者:菅谷 実帆
- PMOコンサルティング事業部
- S/4 HANA認定コンサルタント
「DXの現場」では、ノムラシステムコーポレーションの現役コンサルタントが、SAPの導入をはじめ、DXに20年以上携わった経験から、DXで重要となるポイントについて紹介します。
今回のテーマは「SAPにおける販売管理(SD)モジュールが標準機能でどこまで対応可能か、と15年前のSAPのアップデート」です。
SAPは管理会計(CO)や生産計画(PP)など複数のモジュールからシステムが構成されています。SAP全体の理解を深めるためには、各モジュールへの理解を深めることも重要です。
また、本記事では15年間運用されてきたシステム刷新プロジェクトについてもお伝えします。SAPのアップデートにおける2つの課題とその解決策について、実践的な知見をお伝えします。
販売管理(SD)モジュールとは:物とお金の流れを管理する基幹機能
販売管理(SD:Sales and Distribution)モジュールとは、受注から出荷、請求までの一連の販売プロセスを管理するSAPの中核モジュールです。
簡潔に言えば「物とお金の流れを明確にする」機能を担っています。
そのためSDモジュールも多彩な機能を有していますが、その本質は以下の3つの核となるプロセスに集約できます
- 受注管理: 顧客からの注文情報を受け取り、システム内で受注伝票として記録
- 出荷管理: 商品の物流を管理し、出荷伝票として実績を記録
- 請求管理: 取引の金銭的側面を請求伝票として記録、会計処理との連携を実現
これらの処理を通じて、販売活動の各取引を正確に記録し、在庫管理や会計処理とデータ連携を行います。
SDモジュールで対応できる複雑な価格体系例
販売管理自体は顧客との売買記録がベースとなるため、比較的単純だと思われるかもしれません。しかし、単一製品の価格体系一つとっても非常に複雑です。
- 取引量に応じた段階的割引(ボリュームディスカウント)
- 特定顧客向けの特別価格設定
- グループ企業間での異なる価格体系
これらの価格体系が複数製品にわたり、さらに製品の組み合わせによって追加の値引きが適用されるケースもあります。
個別の取引だけを見れば複雑さは実感しにくいかもしれませんが、システム上はこれらの条件を漏れなく正確に実装する必要があります。
このような複雑な価格体系も現在のSAPでは標準機能で対応可能になっていますが、実際のシステム運用をスムーズに進めるには、業務の背景を理解することが重要です。
そこで、長期間運用されてきたシステムのアップデートの際に業務背景のヒアリングを行った事例をご紹介します。
15年前のSAPをS/4HANAにアップデートするには?

先日私が携わったのは、3か国で200拠点を有する企業様の案件です。15年前に設計されたSAPのSDモジュールをアップデートしました。
アップデートの経緯としては、SAPの保守サポートが2027年で終了することが要因の一つです。
また構築から15年が経過し、システムのパフォーマンス低下や拡張性の限界といった技術的な課題も顕在化していたため、最新のSAP S/4HANAへの移行を決定されました。
この際に採用した手法は、既存のシステムやアドオンをできるだけ活用しながら新環境へ移行する「ストレートコンバージョン」アプローチです。既存の資産を有効活用できるため、比較的低コストでありながら、迅速なシステム移行が可能な手法です。
そのため、当時使っていたSAPに付随していた100個以上のアドオンも、新しいシステムでもそのまま活用しています。
SAPをS/4 HANAにアップデートする際に、アドオンをそのまま用いるのであれば、特別な作業を必要とせずにアップデートできる、と思われるかもしれません。
しかし実際には、以下2点の課題がありました。
- トランザクションコードの見直し
- 業務フローの刷新
順番にご説明します。
1. トランザクションコードの見直し
トランザクションコードとは、SAP内の業務機能にアクセスするための専用コードで、アップデートに伴い機能が追加・変更されたり、機能自体が廃止になることがあります。
そのためアップデート後に、全ての機能を確認した上で、必要に応じてトランザクションコードを正しく修正する必要があります。
2. 業務フローの変更
もう一つの課題は、システムの業務フローが15年前に設計されたもので、現行の業務フローと大きく異なるという点でした。
お客様が使いやすいシステムに構築し直すためにも、システムの業務フローを刷新する必要がありました。
幸いなことに現行の業務フローは、パワーポイントでドキュメント化されていました。
しかし、業務を処理するタイミングなど、長年在籍している方であれば自明であることまでは明記されていません。そのため部外者である私には、業務処理のタイミングや業務間の関連性などが分からず、特に「なぜその業務が必要なのか」という目的も見えにくい状態でした。
製造業では特に、長年かけて形成された独自の業務プロセスが存在し、差別化の要因にもなり得ます。
これらの業務プロセスの背景にある理由や目的を理解せずにシステムを設計すると、表面的には機能を満たしていても、実際の業務との不整合が生じる恐れがあります。
そこで業務フローの再整理のために、担当者の方に詳細なヒアリングを重ね、業務の流れや判断基準、そして各業務の目的などを詳細に把握。その上で業務フローを再度明確化したのです。
あえて「直接対話」にこだわった理由
こうした業務フローの再整理を進める上で私が特に重視したのが「直接対話」の機会です。プロジェクトを成功に導くために、可能な限りお客様との対面での打ち合わせを優先しました。
具体的には、週に1〜2回は必ずお客様先を訪問。13時から17時半頃まで滞在した上で、担当の方々の空き時間を見計らいながらお話を伺っていました。
この直接的なコミュニケーションは一見、非効率に思われるかもしれません。しかし実際には文書だけでは捉えきれない業務の機微や、背景を理解する上で効果的だったと感じています。
例えばある例外処理ルールは、ヒアリング時には話題に登りませんでした。先方が「当たり前」と考えていたからです。何気ない雑談の中で語られたことがシステムを設計する上で実は重要だった、ということは少なくありません。
SDプロジェクトも終盤となった際に、先方から「SD構築完了後も別のプロジェクトに入ってくれたらいいのに」という言葉をいただいた時は、お客様が使いやすいシステムが構築でき、喜んでいただけたのかなと感じ、すごく嬉しかったですね。
まとめ:プロセス一つひとつの目的を理解したい
販売管理(SD)モジュールはSAPを構成する代表的なモジュールの一つです。
SDから生成される販売データはBI(ビジネスインテリジェンス)でも重要な分析対象であり、データドリブン経営には必要不可欠です。
だからこそ、設計・構築は単なる機能実装にとどまらず、業務プロセスの本質を深く理解した上で行う必要があります。システムから生成されるデータの品質は、その基盤となる業務プロセスの設計に大きく左右されるからです。
私たちはデータドリブン経営を支えるためにも、お客様への丁寧なヒアリングを心がけながら、一つひとつのプロセスの目的の理解に努めたいと考えています。
※本記事の内容は2025年3月の情報をもとにしています。記事内のデータや組織名、役職などは制作時のものです。