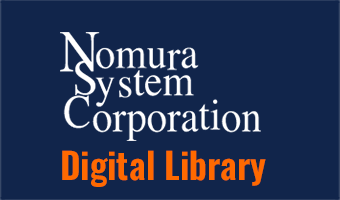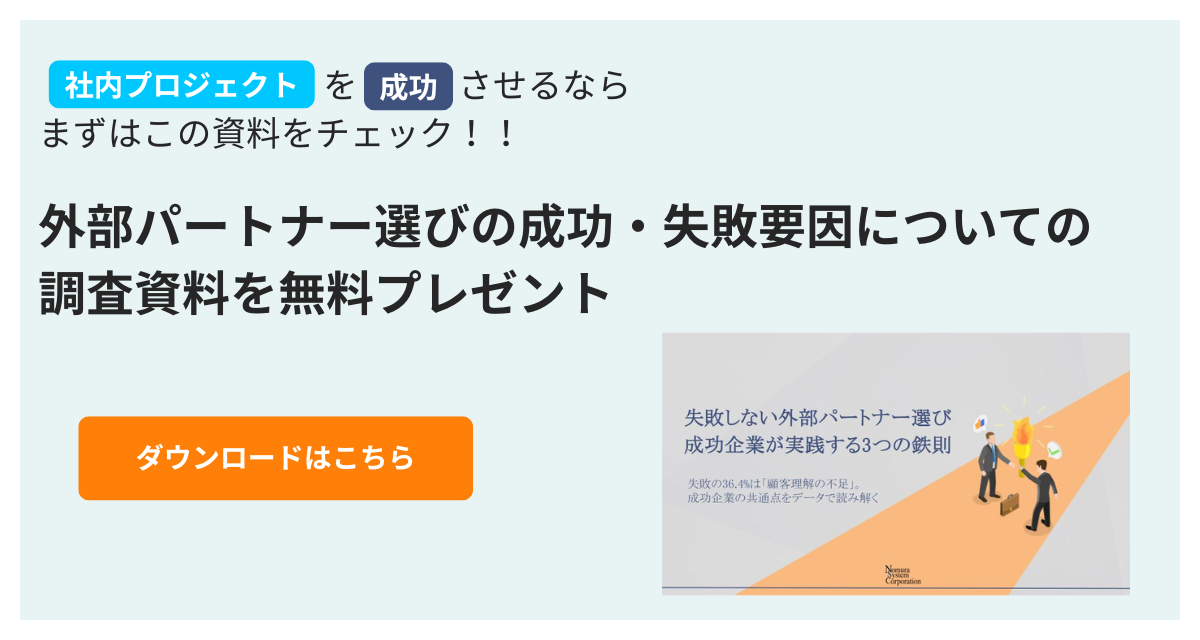DX
インパクト分析とは?目的・手順・指標をわかりやすく解説
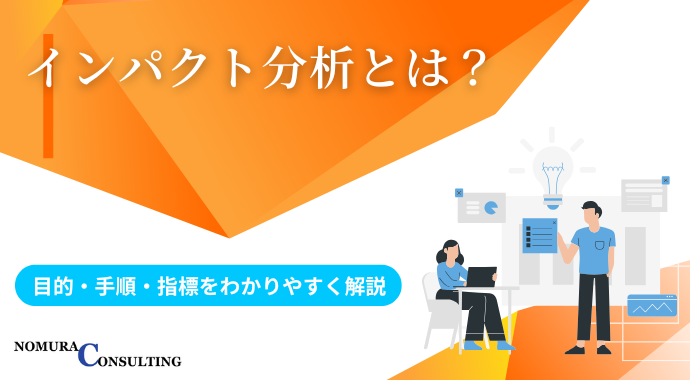
インパクト分析とは、業務やシステムが停止した際に、どの程度の影響が生じるかを評価する手法です。チェンジマネジメントや事業継続計画(BCP)において、影響の範囲や深刻度を把握し、的確な対応策を講じるために活用されます。
本記事では、インパクト分析の目的や進め方、活用される指標についてわかりやすく解説します。
インパクト分析(事業影響度分析)とは|業務停止リスクを可視化する手法
インパクト分析とは、突発的なインシデントなどが、業務やシステムに与える影響を評価・分析する手法です。ビジネス領域では「ビジネスインパクト分析(BIA)」とも呼ばれ、日本語では「事業影響度分析」と訳されます。
災害やシステム障害によって業務が停止した際には、財務的な損失や顧客対応の負担、風評リスクなど、さまざまな影響が発生する可能性があります。また、組織変革にともなう影響を整理する「チェンジマネジメント」においても、「誰に」「どのような影響を及ぼすのか」を把握するための重要なプロセスです。
インパクト分析の主な目的3つ
インパクト分析の主な目的は以下の3つです。
- 潜在的な課題やリスクを可視化する
- 必要なリソースを予測する
- 事業継続計画策定に必要な情報を整理する
それぞれの目的を解説します。
潜在的な課題やリスクを可視化する
インパクト分析の大きな目的のひとつは、プロジェクトや業務の初期段階で潜在的な課題や中断リスクを洗い出し、事前に備えることです。たとえば、システム障害や人員不足など、業務の継続に支障をきたす要因がどこに潜んでいるのかを明らかにし、影響の大きさや範囲を定量・定性の両面から可視化します。
リスクが明確になることで、関係者間での危機意識の共有が容易になり、的確な対策や優先順位の判断にもつながります。その結果、対応の遅れや被害の拡大を未然に防ぎやすくなるでしょう。
必要なリソースを予測する
インパクト分析は、業務の復旧に必要なリソースをあらかじめ予測するうえでも役立ちます。たとえば、人材・設備・ITシステム・重要情報など、業務継続に欠かせない要素について、平常時と非常時のギャップを可視化し、それぞれの種類や数量を予測することが可能です。
こうした分析結果は、復旧の目処を立てる際の判断材料となるだけでなく、リソースの過不足を見直し、優先的に確保すべき対象を明確にします。また、現場の実態と想定とのギャップの把握にもつながるため、定期的な体制強化や教育計画の見直しにも有効です。
事業継続計画策定に必要な情報を整理する
事業を継続していくうえでは、災害やシステム障害、感染症の拡大など、突発的なリスクに備えることが欠かせません。そのためには、「事業継続計画(BCP)」の策定が重要です。
インパクト分析は、業務が受ける財務的・運用的な影響を定量・定性の両面から可視化し、重要業務の特定や復旧の優先順位、目標復旧時間(RTO)の設定に役立ちます。BCP策定に必要な判断材料を整理するうえで、有効な手法といえるでしょう。
さらに、チェンジマネジメントにおける影響把握や対策設計の前提情報としても効果的です。フレームワークとの連携により、業務変更時のリスク評価や利害関係者への影響を事前に把握し、的確な対応につなげやすくなります。
関連記事:チェンジマネジメントのフレームワークとは?特徴と事例で学ぶ成功のポイント
インパクト分析で用いる代表的な指標
インパクト分析では、業務停止による影響を具体的に評価するために複数の指標を用います。とくに、業務の重要度や復旧の優先順位を判断するうえで中核となる指標が以下の2つです。
- 復旧目標時間(RTO)
- 最大許容停止時間(MTPD)
ここでは、代表的な指標としてこれら2つを解説します。
復旧目標時間(RTO)
復旧目標時間(RTO)は、業務やシステムが停止した際に復旧すべきタイミングの目安を示す指標です。BCPやインパクト分析において、停止時に許容できる最大のダウンタイムから逆算して設定します。
また、RTOは、業務の重要度・契約条件・顧客影響などを考慮して、数分〜数日単位で定めるケースが多く見られます。適切に設定されたRTOは、事業継続における最低ラインとなり、復旧計画や資源配分の根拠となります。
最大許容停止時間(MTPD)
最大許容停止時間(MTPD)は、業務停止によって重大な損失や事業継続の危機に至るまでの猶予時間を示す指標です。これを超えると、信用失墜や事業継続困難などのリスクも高まります。
MTPDはRTOよりも広義の概念であり、経営判断や業務の優先順位づけに加え、復旧対策の緊急性を見極める基準として活用されます。また、MTPDとRTOの差から必要な投資規模や対策レベルを見直す材料としても有効です。
インパクト分析の手順
インパクト分析は、一般的に以下の手順で進めます。
- リスクの洗い出し
- 各業務への影響度評価
- 復旧判断に必要な指標の設定
- 分析結果の集計
各工程を見ていきましょう。
リスクの洗い出し
インパクト分析を行う際は、まずリスクの洗い出しから着手します。業務やプロセス単位で事業中断の原因となるリスク要因を抽出する作業は、影響度の評価や復旧計画の立案に必要な基礎データの整備をするうえで欠かせない工程です。
この過程では、災害・システム障害・人材の欠員・外注の停止など、外部的・内部的リスクを幅広く想定する必要があります。特定の分野や部門に偏ることなく、全社的な視点でリスクを捉える姿勢が重要です。加えて、現場へのヒアリングやアンケートを通じて、網羅的に情報を把握することも求められます。
各業務への影響度評価
インパクト分析では、各業務が停止した場合の影響を、定量的評価と定性的評価の両面から分析します。
たとえば、定量評価では売上損失や生産量の低下、定性評価では顧客対応の遅延やブランド毀損などの観点が挙げられます。これらを適切に捉えるためには、以下のような複数の観点から評価することが必要です。
- 財務的損失
- 生産・処理件数
- 顧客への影響
- 法的リスク
こうした評価によって各業務の重要度が可視化され、優先的に対策すべき領域や資源配分の方向性が明確になります。
復旧判断に必要な指標の設定
続いては、インパクト分析における評価結果をもとに、業務の復旧判断に不可欠な重要指標を設定する工程です。指標の内容は業務の性質によって異なりますが、一般的には「復旧目標時間(RTO)」や「最大許容停止時間(MTPD)」などが用いられます。これらは、業務の重要度や他業務との依存関係、外部要因など総合的に考慮して決定することが必要です。
適切な指標の設定により、復旧優先順位が明確になり、限られた資源のなかで迅速かつ合理的な対応や判断ができます。
分析結果の集計
インパクト分析の最終段階は、評価結果をもとにした「分析レポート」の作成です。このレポートは、収集した情報を体系的に整理し、復旧戦略や優先順位の判断に役立つ重要な情報となります。
たとえば、各業務の評価結果を表やドキュメントにまとめておけば、影響の大きさや復旧の優先度を一目で把握可能です。さらに、業務間の依存関係やリスク分布を図で示すことで、関係者の理解が深まり、意思決定にも一貫性が生まれるでしょう。
インパクト分析で事業継続に備えよう
インパクト分析は、業務中断がもたらす影響を定量・定性の両面から「見える化」し、限られたリソースの中で優先的に対処すべき領域を明らかにする手段です。RTOやMTPDなどの指標を活用することで、業務ごとの重要度や復旧の優先順位が明確になります。
また、有事の際の備えだけでなく、チェンジマネジメントにおいても効果的です。BCPの強化にとどまらず、変化に強い組織文化の構築に役立つ手法として継続的な活用が求められます。
DX化などの取り組みにより、チェンジマネジメントの必要性がある場合はノムラシステムコーポレーションまでお問合せください。
東京MXの番組で、ノムラシステムコーポレーションが取り上げられました。詳しい内容を知りたい方は、ぜひ下記のYouTube動画をご覧ください。
ノムラシステムコーポレーションの紹介動画
お問い合わせはこちら