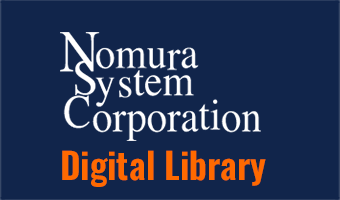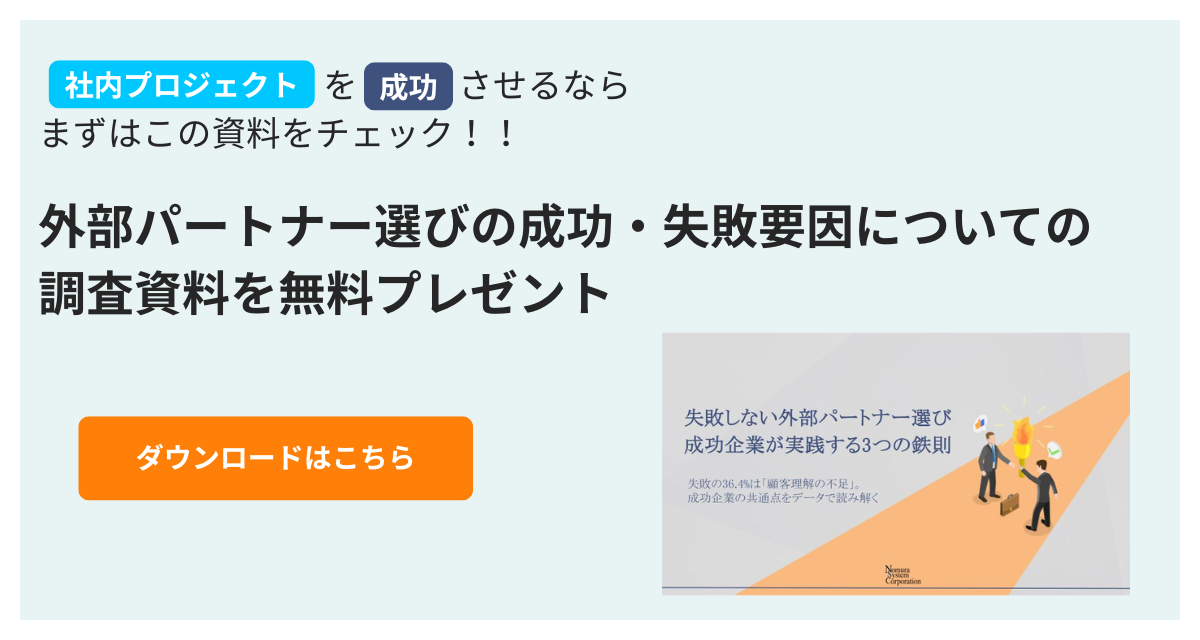コンサルタント記事
「見える化」は改善の第一歩! SAPで二酸化炭素排出量を可視化した結果|DXの現場

- 話者:大熊 千穂
- PMOコンサルティング事業部 マネージャー
- SAP認定コンサルタント(FI)
「DXの現場」では、ノムラシステムコーポレーションの現役コンサルタントが、SAPの導入をはじめ、DXに20年以上携わった経験から、DXで重要となるポイントについて紹介します。
今回のテーマは「SAP導入による社内データの見える化」です。SAP導入の最たるメリットの一つは、社内データがリアルタイムで整理され、分析やレポートによる「見える化」が可能となる点です。
本記事では、BPC(Business Planning and Consolidation)という予実管理をはじめとした事業計画・予算策定機能の「見える化」を紹介するとともに、「見える化」によって企業が成果を上げた事例についてご紹介します。
なお今回ご紹介する予実管理は予算ではなく、CO2量です。どのように「見える化」したのか、楽しみにご覧いただけたらと存じます。
経営管理業務モジュール(BPC)とは?
現在私は、BPCの保守・実装をサポートしています。
BPCとは事業計画策定や予算編成などの機能が統合された経営管理業務モジュールです。
一般的なERPシステムは「実績データを記録する場」であるのに対し、BPCは「将来の計画値を策定・管理する場」と表現できます。
このように、実績と計画を連携させることで、計画の進捗をリアルタイムに確認できるため、経営管理基盤の強化につながります。
また、事業部ごとに計画を策定することもできるため、事業部ごとの予実比較も容易です。
ただ一方、BPCは主に予算策定のタイミングで用いられる機能であるため、使用期間が限られます。そのため、年間を通じて保守が必要なモジュールと比較して専門家が少ない傾向があります。
保守の役割と業務範囲
また私は、PMOコンサル事業部でマネージャーとして、SAPを導入されたお客様に対するシステム保守チームを取りまとめています。
保守業務の役割は、お客様が導入されたシステムが正常に稼働するようサポートすることです。
具体的には、システムのトラブル対応、夜間の障害対応、機能の追加開発からリリース、ヘルプデスク、お客様企業の担当者の方とシステム運用のスケジュールのすり合わせなどをチームで行っています。
私自身はこれまで、スクラッチの保守運用を3年、BW(Business Warehouse:SAPのデータ分析基盤)の保守運用を3年、そして設計に2年ほど携わってきました。
その中には、SAPを導入した企業様が自社でSAPを保守できるように、保守のノウハウを継続的に提供するケースや、排出するCO2量を計算するなど、少し変わった事例も含まれています。
そこで今回は、SAPでCO2排出量も計算可能であることも含めて、具体的にどんなプロジェクトを進めてきたか、を紹介いたします。
SAPでCO2排出量を計算!見える化は排出量削減の第一歩
私が、小売業・BtoCサイト・ECサイトを運営している会社様の保守を担当していたときの話です。
そのお客様は以前SAPを導入した際に、大型トラックを用いた運搬時などに排出されるCO2を計算する仕組みを導入されていました。
しかし同時に、活用にあたっての課題も以下のように感じられていました。
- 「SDGsに取り組むにあたり、CO2量をより精緻に算出したい」
- 「CO2量の分析レポートはあるが、活用できていない」
ご存じの方も多いかと思いますが、SDGsの観点からもCO2量の測定市場は大幅に成長しています。レポートによってばらつきはありますが、年平均3.99% 〜 10%の成長率が見込まれるそうです。
これまでに売上のレポートの構築経験は複数ありますが、CO2量の可視化はそれまで実施したことはなかったため、お客様と2人3脚でこの課題に取り組みました。
引用:世界の高度なCO2センサ市場規模シェア | パノラマデータインサイト
より精緻なCO2排出量を算出するために
前提としてこの時の状況は、以下のような形でした。
- CO2排出量マスターは構築済み
- より精緻な値を算出するためにマスターへのデータ追加が必要
もう少し具体的にお伝えしますと、CO2排出量マスターには、
- トラックが1キロ走った際のCO2排出量(kg/km)
- 拠点間ごとの距離(km)
- 積載量におけるトラックのCO2排出量(変数)
といったデータは存在しました。
そのため、あるトラックが何tの商品を乗せて移動した場合のCO2排出量は以下のように計算できます。
| トラックが1キロ走った際のCO2排出量 × 拠点間の距離 × 積載量におけるトラックのCO2排出量 |
この式を見ると、一見、問題ないようにも見えます。しかし、さらにデータを精緻にすることもできます。
例えば積載量。
複数拠点で荷下ろしした場合、荷下ろしした商品の重量によってCO2排出量は異なります。しかし商品によっては、重量がマスターに格納されていない場合もあり、精緻な数値が算出できません。
この場合、マスターに情報を追加することはもちろん。すでにSAPを導入されているお客様でしたので、出荷伝票と紐づけることで、具体的な積載量の変化を算出。計算した積載量の変化によってCO2排出量も変化させることで、より緻密に排出量を算出することができました。
例えば廃盤になった商品等、重量を測定できない場合などは、近似値を代入することで、できるだけ正確な値を算出できるように努めています。
このような形で、担当者様と一緒に他にも精緻にできそうな値や計算式を一つずつ検討し、この課題に取り組んでいったのです。
プロジェクト終了後しばらく期間が空いた後ではありますが、Yahoo!ニュースでその企業様がCO2排出量を削減したと掲載されていました。
自分がどのくらいお役に立てたかは定かではありませんが、そのニュースを見た時はすごく嬉しかったですね。
「見える化」にこだわりたい
私は「なるべく見える化する」ということを意識して業務にあたっています。
上記からの文脈で言えば、数値データの見える化だと思われるかもしれませんが、お客様とのお話しする際や自社でのミーティングでも同様です。
例えば社内で、システムの技術者同士でもイメージの共有が難しいと思った際には、Excelを用いてできる限り図式化することで、認識の齟齬が無いように努めています。
先ほどの環境レポートでも、積載量まで加味した上でCO2排出量を算出したい! というご要望をいただいた際など、私自身では思い至らないような視点をいただくことは多々あります。
だからこそ、どのようなデータが分かっていて、何が分かれば算出できるのか?といった情報を見える化することで、お客様と一緒になって考え、提案できるよう努めています。
まとめ:見える化によって次の一歩が生まれる
CO2排出量の事例のように、SAP導入をはじめとしたDX化には「見えなかったもの」を「見える化」する力があります。
「見えないもの」の改善は困難で、何を改善するべきなのか。そして、本当に改善できたのかは、感覚に頼るしかありません。そのため「見える化」することは、あらゆる改善のための第一歩なのです。
DXの本質は、単なるシステム導入ではなく、データを活用した意思決定と改善のサイクルを生み出すことであると私は考えています。
だからこそ、どのような改善を行うために、どのようなデータを見える化するのか、をお客様と一緒に考え、改善の第一歩としたいと思っております。
※本記事の内容は2025年3月の情報をもとにしています。記事内のデータや組織名、役職などは制作時のものです。