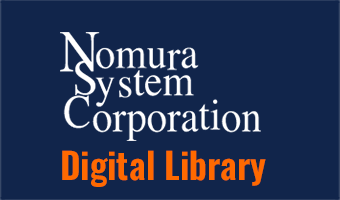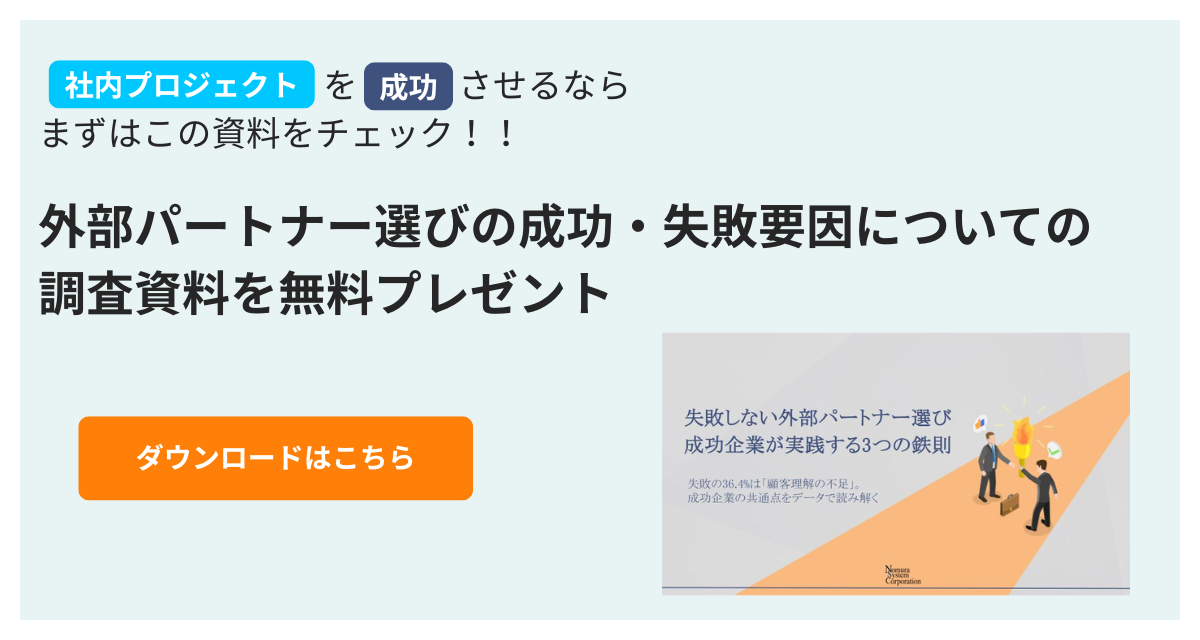DX
ステークホルダー分析とは?チェンジマネジメントにおける役割と進め方
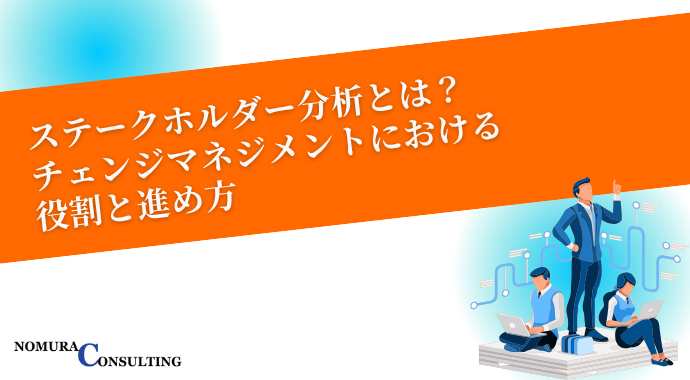
ステークホルダー分析とは、組織の取り組みに関わる関係者を把握し、適切な関与や対応を検討するための手法です。チェンジマネジメントやDX推進など、変化を伴うプロジェクトでは、関係者の理解と協力を得ることが欠かせません。
本記事では、ステークホルダー分析の基本的な考え方や具体的な進め方、活用できるフレームワークをわかりやすく解説します。
ステークホルダー分析とは|チェンジマネジメントに向けた関係者の整理
ステークホルダー分析とは、チェンジマネジメントにおける戦略立案の起点として、変革に関わる人や部門を洗い出し、それぞれの影響力や注目度を整理する手法です。
組織変革では、意思決定層や現場担当者はもちろん、間接的に影響を受ける部門や外部パートナーも含めた幅広い利害関係者が存在します。こうした人物の可視化により、従来見落とされがちだったニーズや連携可能な部門、人物を再発見することが可能です。
DX推進のような全社的な取り組みでは、初期段階でのステークホルダー分析がプロジェクト全体の成果を左右するケースも少なくありません。変革に向けた足並みを揃えるためには、分析結果を元にした戦略的な計画が求められます。
ステークホルダー分析の重要性
ステークホルダー分析が重要視されるポイントとして、主に以下の2つの理由が挙げられます。
- 影響力のある関係者を見極める
- 潜在的なリスクを未然に防ぐ
影響力のある関係者を見極める
プロジェクトを成功へ導くためには、意思決定に影響を及ぼすキーパーソンの把握が不可欠です。ステークホルダー分析を通じて、関係者の中から影響力の高い人物を特定し、効果的にアプローチしやすくなります。
とくにチェンジマネジメントでは、役職や部署にとらわれず、実質的にプロジェクトを動かす人物や、現場の意見を左右する支援者を見極めることが重要です。組織内外のネットワークが可視化されると、これまで気づかなかった協力者の存在にも気づくことができます。
こうしたキーパーソンの特定は、意思決定のスピードや変革の成否を左右する要素のひとつです。
潜在的なリスクを未然に防ぐ
ステークホルダー分析は、関係者の利害や立場を整理し、対立や誤解といったリスクを未然に防ぐことができます。とくに多部門が関わる変革プロジェクトでは、予期せぬ摩擦や調整の混乱を防ぐ観点からも欠かせません。
DX化などのプロジェクトにおいて、協力が必要な人物を見落とすと、情報共有が滞り、重要な判断に支障をきたす可能性もあります。あらかじめ関係性を把握しておけば、対話や調整の優先順位が明確になり、合意形成の円滑化がスムーズに行えます。プロジェクト全体の安定性と実行力を向上させるには、初期段階における分析が大切です。
ステークホルダー分析の手法
ステークホルダー分析は、以下の3つのステップで進めるのが一般的です。
- ステークホルダーを洗い出す
- ステークホルダーを分類する
- ステークホルダーに優先順位をつける
それぞれのステップについて、具体的に解説します。
ステークホルダーを洗い出す
はじめに、プロジェクトに関与・影響を及ぼす全てのステークホルダーを洗い出します。「影響を受ける人」「影響を与える人」「抵抗の可能性がある人」など、立場や視点を変えて多角的に抽出することが大切です。思い込みにとらわれず、現場の担当者や外部関係者まで視野を広げましょう。
関係者を把握しきれない場合は、プロジェクトメンバーとのブレインストーミングや関連部署・専門家へのヒアリングを取り入れると見落とし防止につながります。組織全体の力を活かすためにも、初期段階での丁寧な洗い出しが欠かせません。
関連記事:チェンジマネジメントのフレームワークとは?特徴と事例で学ぶ成功のポイント
ステークホルダーを分類する
続いて、抽出したステークホルダーを「影響力」「関与度」「協力度」などの軸で分類します。たとえば、関心度が高く積極的に関与したいと考えている人物に対しては、初期段階からこまめに情報共有し、信頼関係を築くことで協力を得やすくなります。
一方で、関心度が低いが影響力の大きい人物には、段階的に理解を得る工夫が求められるでしょう。
分類する際は、単一の視点に偏らず、複数の観点を組み合わせて整理すると、関与方法や調整の優先順位が明確になります。誰にどうアプローチするかを戦略的に判断するうえで、重要な役割を果たす工程です。
ステークホルダーに優先順位をつける
分類したステークホルダーに対しては、影響力・関与度・懸念点などの特性をさらに掘り下げて優先順位をつける必要があります。プロジェクトとの関係性や期待される役割を踏まえて、どの関係者にどの程度のリソースや時間を割くべきかを明確にすることが目的です。
影響力が大きく協力的な人物には、継続的な関与や意見の反映を通じてプロジェクトの推進役となってもらうアプローチを検討するとよいでしょう。一方で、影響力が小さく優先度が低い関係者に対しても、必要最低限の情報共有によって、不安や不信感の芽を未然に防ぎやすくなります。このように、優先順位づけは、限られたリソースを最適に配分するために重要です。
ステークホルダーの分析に使える3つの手法
ステークホルダーの分析には、以下の3つのツールが役立ちます。
- CVCA|顧客起点で関係者の流れを可視化する
- ステークホルダーマップ|関係性と優先度を視覚的に整理する
- PMBOK|体系的なフレームワークで関係者の影響度を分析する
それぞれの特徴を解説します。
CVCA|顧客起点で関係者の流れを可視化する
CVCA(Customer Value Chain Analysis)とは「顧客価値連鎖分析」の略称で、顧客にとっての価値がどのようなプロセスで生まれているのかを可視化するための手法です。事業やプロジェクトに関わるステークホルダーが関与するタイミングや目的を明確にすることで、それぞれの役割や価値を把握できます。
また、プロジェクト全体の構造とステークホルダーの関係性を俯瞰しやすくなる点も特徴です。活用により、ボトルネックの発見や課題解決につながるほか、ユーザー視点を軸にしたサービス設計や関係者同士の連携強化にも応用できます。
ステークホルダーマップ|関係性と優先度を視覚的に整理する
ステークホルダーマップとは、洗い出した関係者を図式化し、影響力や関心度といった軸に基づいてマッピングする手法です。各ステークホルダーがプロジェクトに対してどの程度の影響を持ち、どれだけ関心を寄せているかを視覚的に整理することで、優先的に対応すべき対象が明確になります。
たとえば「影響力が高く関心も高い層」は継続的な関与と情報共有が重要であり、「影響力は高いが関心が低い層」にはモチベーション向上を意識した働きかけが重要です。ステークホルダーマップの活用は、各関係者に対するアプローチ戦略の設計や利害調整がスムーズに進み、プロジェクトの成功率向上につながる取り組みといえます。
PMBOK|体系的なフレームワークで関係者の影響度を分析する
PMBOK(Project Management Body of Knowledge)は、プロジェクトマネジメントの知識や手法を体系的にまとめた国際標準のガイドラインです。このツールでは、ステークホルダーの特性を、影響度・関与度・利害関係といった軸から整理し、戦略的に関与させていくアプローチが重視されています。
一般的に用いられる分析基準は以下の4つです。
- 権力と関心度
- 権力と関与度
- 関与度と影響度
- セイリエンス・モデル(権力・正当性・緊急性)
いずれも、プロジェクトの推進において「誰に」「いつ」「どのように」働きかけるべきかを明確化するのに役立ちます。
なお、PMBOKでは、具体的な手法までは示されているわけではないため、実践する際は、自社のプロジェクト規模や組織文化を踏まえて、適切な基準やフレームワークを柔軟に適用する必要があります。
ステークホルダー分析で適切な関係構築を始めよう
ステークホルダー分析は、関係者の影響度やスタンスを把握し、的確な対応方針を立てるうえで重要なプロセスです。とくに、チェンジマネジメントにおいては、組織内の抵抗を最小限に抑え、DXといった変革をスムーズに進めるためにステークホルダーの協力が欠かせません。早期の段階から関係者を巻き込み、合意形成を図ることで、プロジェクトの成功率も高まります。
DX化などの取り組みにより、チェンジマネジメントの必要性がある場合はノムラシステムコーポレーションまでお問合せください。
東京MXの番組で、ノムラシステムコーポレーションが取り上げられました。詳しい内容を知りたい方は、ぜひ下記のYouTube動画をご覧ください。
ノムラシステムコーポレーションの紹介動画
お問い合わせはこちら