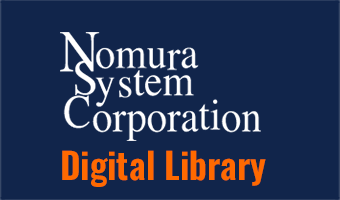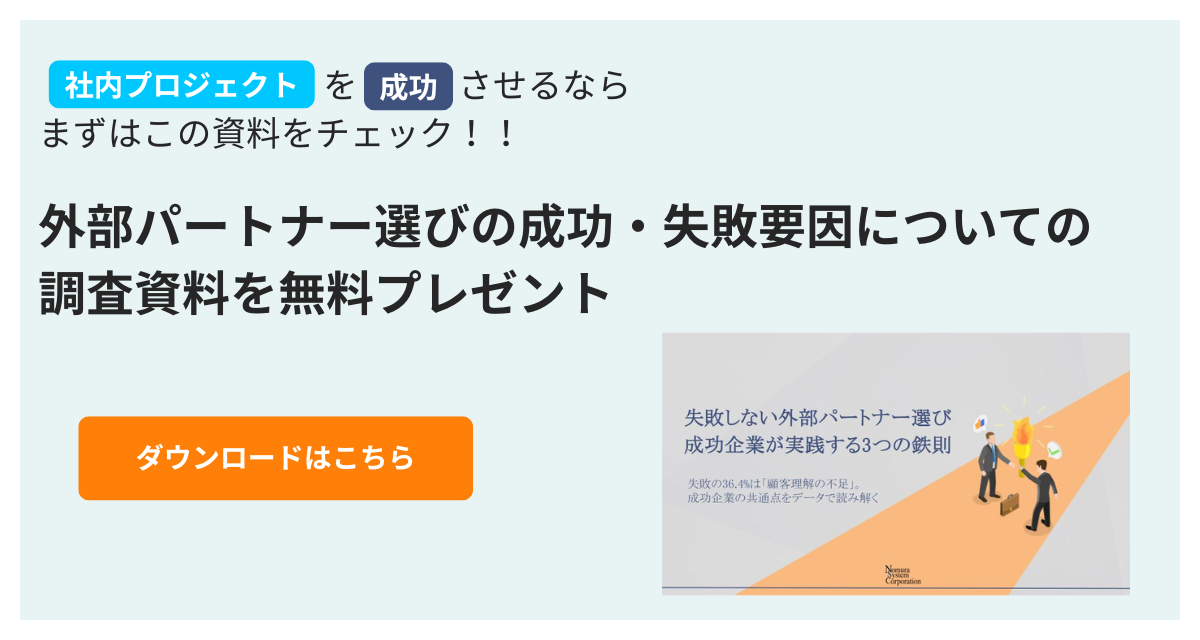DX
小売DXとは?求められる理由や成功に向けた課題を解説
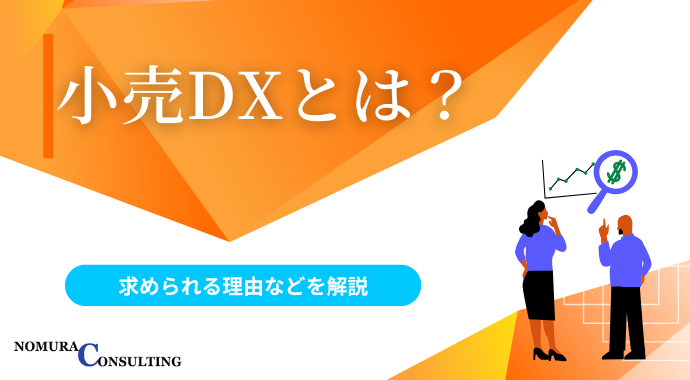
小売DXとは、消費者の購買行動の変化や人手不足・物流課題など構造的な問題が深刻化するなかで注目されているデジタル活用による業務改革です。
本記事では、小売DXが求められる背景や成功に向けた課題、事例をわかりやすく解説します。
小売(リテール)DXとは|業務改革と顧客満足を両立するデジタル戦略
小売(リテール)DXとは、ECやSNSを通じたオンライン購買の普及やサステナビリティへの関心の高まりなど、急速に変化する消費者の購買行動や価値観に対応するためのデジタル改革です。
店舗業務の効率化に加えて、物流・メーカー・卸売といったサプライチェーン全体とのデータ連携によって、業務効率と顧客満足の最大化を両立させる役割も担います。
小売DXは、早い段階からDXを進めている情報通信業や金融業などと比べると遅れを取っている状況です。
2021年3月に株式会社情報通信総合研究所が発表した報告書によると、2018年以前からDXに取り組んでいる企業は、情報通信業(放送業)が46.2%、卸売業・小売業では22.8%でした。
参考:デジタル・トランスフォーメーションによる経済へのインパクトに関する調査研究の請負|株式会社情報通信総合研究所
小売DXが求められる主な理由3つ
小売DXが求められる理由は、主に以下の3つです。
- 部門間や企業間での情報伝達をスムーズにするため
- 顧客ニーズや消費行動の変化に対応するため
- 業界の構造的課題を解決するため
本項では、それぞれの理由をわかりやすく解説します。
部門間や企業間での情報伝達をスムーズにするため
小売DXが求められる理由は、社内外の情報伝達の非効率を解消し、連携をスムーズにするためです。
従来の小売業では、小売店や物流、メーカーなどの間で情報が分断される傾向にあり、サプライチェーン全体の状況を見通しにくい点が大きな課題でした。
小売DXに取り組むことで、商品の規格や商品コードなどの情報(商品マスタ)が共有化され、小売店もメーカー側の在庫状況を把握しやすくなります。
また、社内の各部門でデータの一元管理が進むことで、課題の可視化だけでなく、スピーディな意思決定も可能です。
部門間で分断されていた情報を繋ぎ、共有できる体制を構築することは、小売DXが求められる背景となっています。
顧客ニーズや消費行動の変化に対応するため
変化する顧客ニーズや消費行動に対応するためには、小売DXの推進が必要です。
消費者の行動は、オンラインとオフラインを横断的に活用する形へと変化しています。
チャネルごとに異なるデータが管理されていると、在庫確認や購入履歴の把握が困難になり、スムーズな顧客体験を妨げかねません。
たとえば、双方のチャネルを連携させることで、顧客満足の維持・向上が期待できます。
また、商品そのものの価値に加えて、原材料や製造日、生産地といった情報の可視化も消費者の関心を集めています。
その対策として、スマートフォンをかざすだけで情報にアクセスできるバーコードやQRコードの活用など、デジタル技術を通じた情報提供も重要です。
変化する消費行動や価値観に対応するためには、小売DXを通じたチャネル統合や情報提供の強化が欠かせません。
業界の構造的課題を解決するため
小売DXは、業界が抱える構造的な課題を解決するために求められています。
日本の小売業界では、物価高やレガシーシステムなど業界全体や社会の仕組み自体に起因する構造的な課題を抱えています。
とくに人手不足は深刻な問題であり、業務の効率化や自動化を目的としたDXの推進が急務です。
その一例である、トラックドライバーの不足や労働時間の上限規制から懸念される「物流の2024年問題」は、納品遅延や物流コスト増など、小売業にも大きな影響を与えています。
こうした課題に対して、需要予測や自動発注システムなどを導入することで、業務の属人化を解決するだけでなく、業務効率の改善も期待できます。
発注から品出しに至るまでの全工程を見直し、効率化を図る小売DXは、業界全体の持続可能性に直結する取り組みです。
関連記事:レガシーシステムとは?問題点や原因、脱却する方法をわかりやすく解説
小売DX成功に向けた主な課題
小売DX成功に向けた課題は、主に以下の3つです。
- 社内外の情報連携が困難
- 消費者と企業間における価値観のギャップ
- 属人化による作業のばらつき
本項では、それぞれの課題をわかりやすく解説します。
社内外の情報連携が困難
社内外を問わず販売・在庫・物流などでシステムが統一されていない場合、情報共有がスムーズに行えず、DX推進の大きな障壁となります。
とくに小売業では、メーカーや卸など外部との連携が不可欠であり、複雑な構造で成り立っているため、環境整備が進んでいないケースも少なくありません。
加えて、オンラインとオフラインのチャネルが分断されていると、在庫状況や購買履歴、顧客対応に関する情報が一元管理できず、顧客体験や業務効率に悪影響を及ぼします。
小売DXを進めるには、社内の各部門はもちろん、外部パートナーとも連携できる共通のシステム基盤を整備し、業務プロセスをシームレスに繋ぐ体制づくりが不可欠です。
消費者と企業間における価値観のギャップ
消費者ニーズが多様化・細分化するなかで、企業側がそのすべてを把握しきれず、消費者とのあいだに価値観のギャップが生じやすくなっています。
これも小売DXを妨げる課題のひとつです。
たとえば、競合と同じサービスを提供していても、自社の顧客層のニーズを満たしていなければ選ばれない可能性があります。
さらに、地域や店舗によって求められる商品やサービスが異なる場合もあるでしょう。
こうした状況に対応するには、小売DXを通じて顧客ごとの行動や嗜好を可視化し、的確なマーケティングや商品展開につなげることが大切です。
消費者が本当に求める価値を見極め、適切な形で提供できれば、小売DXの成果の最大化が期待できます。
属人化による作業のばらつき
小売業では、業務が担当者ごとに分担されやすく、属人化が課題となっています。
これがDX推進の妨げとなっているのです。
たとえば、発注管理では需要の見極めや判断が求められるため、担当者のスキルに差があるとロス率が高まる恐れがあります。
DXツールやAIの導入によってリアルタイムな在庫管理が可能になりますが、自社の戦略や現場の実態に即していなければ、十分な効果は期待できません。
加えて、従来のやり方にこだわる意識が、変革の妨げになることもあります。
小売DXを成功させるには、属人化を解消するとともに、DXの必要性を現場で理解し、運用できる人材の育成も重要です。
関連記事:業務属人化の解消方法、解消するメリットや解消に役立つツールを解説
小売DXの成功事例
小売DXで成功した事例を2つ紹介します。
- DXによる業務効率化でEC店舗の売上が拡大|有限会社小西タイヤ
- デジタル技術の活用で顧客満足度が向上|株式会社鈴花
DXによる業務効率化でEC店舗の売上が拡大|有限会社小西タイヤ
有限会社小西タイヤでは、タイヤのピッキングなど物理的な業務に追われ、販売戦略を練る時間を確保しづらい点が課題でした。
この状況を打開するため、社長直下に「DX推進チーム」を設置し、2027年までに達成すべきDXの目標を数値で明確に定め、毎月その進捗を評価しています。
加えて、基幹システムやハンディ端末の導入、RPAの活用、データベース化した顧客情報に合わせたメール配信により、業務時間の短縮と売上向上を両立している点が特徴です。
こうした取り組みにより、業務全体の効率が向上し、従業員がより付加価値の高い業務に注力できる環境が整いました。
オンライン経由での売上増加にもつながっています。
デジタル技術の活用で顧客満足度が向上|株式会社鈴花
老舗呉服店の株式会社鈴花では、顧客とのつながりを重視する一方で、顧客情報が担当者の記憶や手書きのメモに依存しており、ノウハウの属人化が課題となっていました。
そこで、情報を会社の資産として活用するために、顧客情報のデジタル化を進め、全社で共有できる仕組みを導入しています。
さらに、データ分析にも力を入れたことで、顧客ごとに適した提案が行える環境も整備されました。
また、顧客と直接繋がれるLINEアカウントも開設し、顧客接点を強化した点も特徴です。
コミュニケーションの活性化により、LINE経由の売上は前年比113%を記録しています。
小売DXは顧客満足度と業務変革を両立する取り組み
小売業におけるDXは、情報の分断や業務の属人化といった現場の課題を解決するだけでなく、消費者との価値観をすり合わせるうえでも重要な取り組みです。
DX推進により、顧客満足度と業務変革の両立を目指しましょう。
こうしたDX推進を支援するパートナーとして、ノムラシステムでは、専属のコンサルタントがDX推進をサポートします。
DXの導入でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
東京MXの番組で、ノムラシステムコーポレーションが取り上げられました。詳しい内容を知りたい方は、ぜひ下記のYouTube動画をご覧ください。
ノムラシステムコーポレーションの紹介動画
お問い合わせはこちら