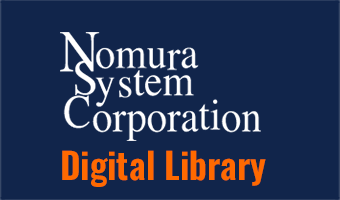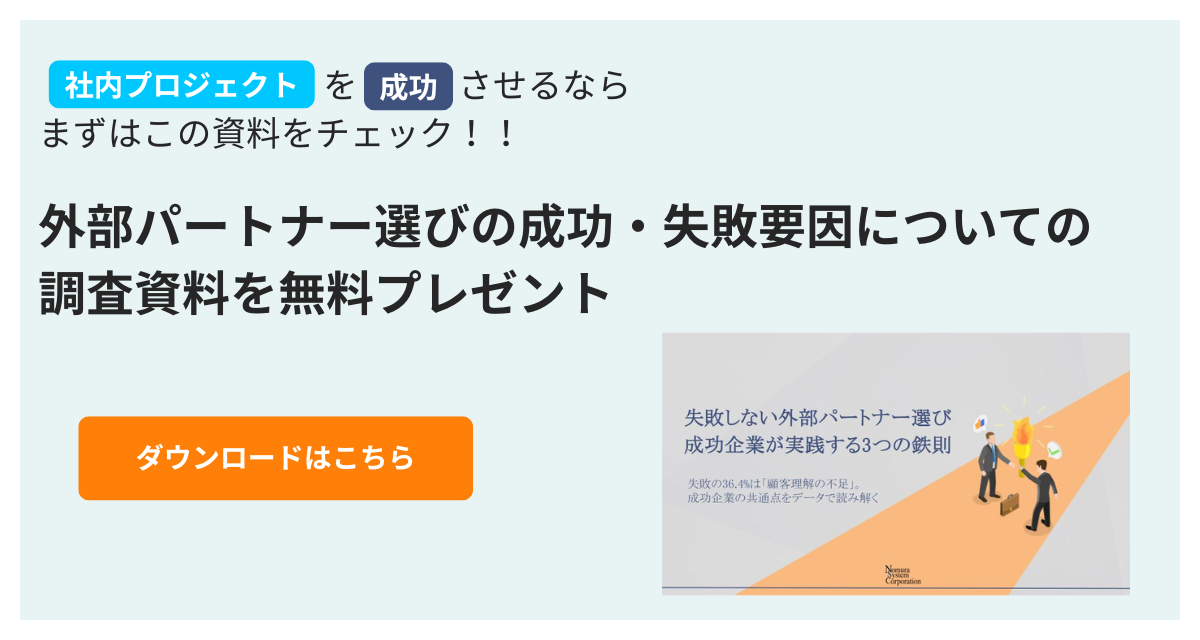PMO
スコープマネジメントとは?目的や手順、注意点をわかりやすく解説!
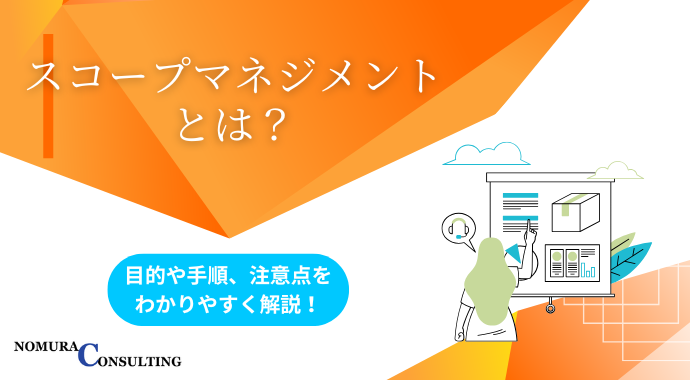
複雑なプロジェクトほど、作業範囲が曖昧になり、追加作業や認識のズレから納期の遅延やコストが膨らみやすくなります。このような課題を防ぐために重要なのが「スコープマネジメント」です。
本記事では、スコープマネジメントの基本的な考え方や実践手順、注意点をわかりやすく解説します。
スコープマネジメントとは「プロジェクトの作業範囲を定義して管理を行うこと」
スコープマネジメントとは、スコープ計画・スコープ定義・WBS作成・スコープ検証・スコープコントロールの5つのスキルが求められるプロジェクトマネジメント手法の一つです。
参考記事:スキル領域とスキル熟達度 (5)プロジェクトマネジメント|情報処理推進機構
具体的には、スコープ計画の管理方針を定め、スコープ定義とWBS作成で作業内容を具体化します。その後、スコープ検証で成果物の適合性を確認し、スコープコントロールで変更や追加作業を抑制します。
目的は、どこまでが実施すべき作業(=スコープ内)で、どこからが対象外の作業(=スコープ外)かを定義し、関係者間で共通認識を形成することです。例えば、通販アプリを開発する場合は、商品検索や購入機能はスコープ内ですが、ECサイトの制作やロゴのデザインはスコープ外です。
スコープの境界を明確にしておくことで、契約範囲外を超えた作業の発生を防ぎ、想定外のコスト増加や納期遅延を抑えられます。
スコープマネジメントとあわせて、押さえておきたい重要なマネジメント手法は以下の記事でご確認ください。
関連記事:プロジェクトマネジメントとは?重要性や手順、注意点について解説
スコープマネジメントの目的
スコープマネジメントの主な目的は、関係者が求める成果物を正確に把握し、限られた期間と予算の中でプロジェクトを確実に遂行することです。ステークホルダーのニーズを的確に捉え、満足度の高い成果物の提供を最終的なゴールとします。
しかし、現実的には限られたリソースの中で、顧客の多様な要望をすべて満たすことは困難です。そのため、スコープマネジメントにより顧客の要望を優先順位付けし、実現範囲をスコープとして定義することで、作業の重複や漏れを防ぎ、品質・コスト・納期の最適なバランスを実現します。
スコープの種類
スコープマネジメントで管理するスコープは、定義対象の違いにより以下の2種類に分けられます。
- プロダクトスコープ
成果物そのものの機能や性能を定義 - プロジェクトスコープ
成果物を完成させるための作業範囲を定義
これらを混同すると、対応範囲が曖昧になり、スコープクリープや関係者間の認識のズレを招くため留意しましょう。
そのため、PMOはスコープの定義と管理を正確に行い、プロジェクト全体の品質や進行を統制する必要があります。
PMOに求められる具体的な役割は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:PMOの役割とは?PMとの違いや導入するメリット、ポイントを解説
【6ステップ】スコープマネジメントの基本的な流れ
スコープマネジメントは、以下の6つの手順で体系的に進めます。
- スコープマネジメント計画の立案
- 要求事項の収集~要求事項トレーサビリティ・マトリックス(RTM)の作成
- スコープの定義
- 作業分解構成図(WBS)の作成
- スコープの妥当性検証
- スコープのコントロール
1.スコープマネジメント計画の立案
スコープマネジメントの最初のステップは、計画の立案です。プロジェクト憲章(*1)やプロジェクト計画書をもとに、スコープの管理方法・責任者・手順を明確化します。
方針決定後は、以下2種類の計画書を作成します。
- スコープマネジメント計画書
スコープの定義・検証方法などの方針をまとめた書類 - 要求事項マネジメント計画書
顧客からの要求事項を整理し、メンバーの具体的な行動方針をまとめた書類
予期せぬ変更にも対応できるように、スコープに影響するあらゆるリスクを想定した柔軟な計画案を立案しましょう。
*1:プロジェクト憲章とは、プロジェクトの目的・前提条件・リスク・予算・ゴールなどを定めた文書のこと
2.要求事項の収集~要求事項トレーサビリティ・マトリックス(RTM)の作成
次に実施するのは、顧客からの要求事項の収集です。プロジェクト憲章や個別インタビュー、アンケートなどを参考に、顧客の意見を正確に把握し、スコープを具体化します。
そして、得られた要求を整理し、以下のようなRTM(*2)を作成します。
| No | 要求概要 | 対応する成果物 | 担当者 | 状況 |
| 1 | 会員登録後にマイページを閲覧できるようにする | 会員管理機能 マイページ画面 | A | 完了 |
| 2 | 商品検索でカラー・価格を絞り込みできるようにする | 商品検索機能 | B | 対応中 |
| 3 | 注文データをCSV出力できるようにする | 受注管理モジュール | C | 着手前 |
RTMを作成することで、要求の漏れを防ぎつつ、担当者間で共通認識を持って作業を進められます。
*2:RTM(要求事項トレーサビリティ・マトリックス)とは、要求と成果物を対応付けて管理する表のこと
3.スコープの定義
要求事項の収集が完了したあとは、プロジェクトスコープ記述書内でプロジェクト全体の成果物と作業範囲に関するスコープを定義します。
プロジェクトスコープ記述書とは、作業範囲・成果物・前提条件・制約条件をまとめた文章です。
定義されたスコープは、プロジェクト全体の判断基準となり、進行や品質管理の目安になります。顧客や社内チームと連携し、内容を精査することで、リスクを早期発見できます。
4.作業分解構成図(WBS)の作成
スコープが確定したあとは、WBS(*3)を作成します。
WBSには2種類あり、プロダクトスコープをもとにしたWBSは最終成果物が明確な短期プロジェクトに、プロジェクトスコープのWBSは成果物が定まりにくい中長期プロジェクトで主に活用されます。
作成手順と例は、以下のとおりです。
- プロジェクトスコープ記述書を確認
目的・成果物・範囲を整理 - フェーズを設定
設計や開発など大項目を定義 - タスクへ分解
各フェーズを細分化して作業単位まで落とし込む - WBSにまとめる
タスクを整理し、進捗・コスト管理できるように一覧化
| フェーズ | 作業項目 | タスク | 担当者 | 期間 |
| 設計 | 基本設計 | 要件整理 | A | 5日 |
| 開発 | フロント実装 | UI作成 | B | 7日 |
| テスト | 単体テスト | 不具合修正 | C | 3日 |
WBSにより担当者と作業内容を整理しておくと、作業の抜け漏れを防ぎ、進捗をスムーズに管理できます。
*3:WBS(作業分解構成図)とは、プロジェクトを小さな作業単位に分解し、階層的に整理する手法のこと
5.スコープの妥当性検証
次に、定義したスコープが適切かをステークホルダーに確認してもらいます。
具体的な確認ポイントは、以下のとおりです。
- スコープがプロジェクトの要求事項を満たしているか
- 予算・スケジュール・リソースなどの制約条件内で実現可能か
- 成果物が受け入れ基準を満たしているか
また、プロジェクトの各過程においては以下のような成果物の妥当性検証も必要です。
- 品質管理の工程で要素成果物を確認する
- ステークホルダーに要素成果物の確認を依頼して合意を得る
妥当性の検証後、要素成果物は受け入れ済み要素成果物となります。
6.スコープのコントロール
プロジェクト進行中は、計画したスコープが達成に向けて適切に進行しているかを定期的に確認します。
進行中の作業が当初の計画と一致しているかを確認し、必要に応じて調整を行います。特に、要件変更が生じた場合や成果物がスコープの定義に達していない場合は、影響範囲を分析し、リソース配分や計画の見直しが必要です。
具体的には、以下のような取り組みを行います。
- スコープレビュー
計画と実績を照らし合わせ、未着手・過剰対応・重複作業などを早期に発見 - 成果物レビュー
品質や要件の達成度を定期的に確認し、改善点を明確化 - 関係者フィードバック
現場・顧客・マネジメント層の意見を共有し、優先度別に改善を反映
このようなレビューやフィードバックを定期的に行えば、変化に強い運営体制を築けます。
スコープマネジメントの注意点
本章では、スコープマネジメントを実践する際の注意点とその解決策を紹介します。
- スコープクリープの発生
- ステークホルダーと作業者間の認識のズレ
スコープクリープの発生
スコープクリープとは、プロジェクトの途中で要件や仕様の追加が繰り返され、作業範囲が膨む現象です。明確なスコープの管理ルールがないまま要件変更を受け入れると、納期遅延やコスト増加を招き、結果として品質低下につながります。
スコープクリープを防ぐためには、スコープの合意内容を文書で残すなど、全関係者がスコープを確認できる仕組みを整えると効果的です。また、変更リクエストが発生した際は、影響範囲や必要なリソースを客観的に検討し、優先順位をつけて対応することで、プロジェクト全体のバランスを保てます。
スコープクリープは、プロジェクト遅延を引き起こす要因の一つです。進行中の案件で納期やタスクの遅延が見られる場合は、早期に対策を講じることが重要です。
プロジェクト遅延の対策を詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
関連記事:プロジェクトが遅れる7つの原因とは?3つのリカバリ方法や事前にできる対策を解説!
ステークホルダーと作業者間の認識のズレ
顧客・営業・開発などの立場によってスコープの理解が異なると、納期遅延や品質低下などのトラブルが生じます。特に、要求事項の定義が曖昧なまま進行すると、成果物の方向性が途中で変わり、手戻りが発生するリスクが高まります。
認識のズレを防ぐには、立ち上げ段階で役割と責任範囲を明確にし、文書を通じて共通理解を持つことが有効です。文書化とレビューを続けることで、認識の差を早期に把握でき、プロジェクトの安定運営につなげられます。
スコープマネジメントを取り入れてプロジェクト成功率を高めよう
プロジェクトの成功には、スコープの明確な定義と継続的な管理が欠かせません。
スコープマネジメントを適切に運用できると、関係者の成果物・作業範囲に関する共通認識が生まれ、限られた時間とリソースで成果を得られます。また、ステークホルダーのニーズを的確に満たし、満足度を高めることも可能です。
スコープマネジメントと組み合わせると効果的な顧客満足度向上のポイントは、以下の記事で詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
関連記事:顧客満足度を向上させる5つのポイント!評価方法や成功事例について解説
ノムラシステムでは、プロジェクトの立ち上げから運用までを支える伴走型のコンサルティングを提供しています。スコープマネジメントの運用でお困りの方は、ぜひご相談ください。
東京MXの番組で、ノムラシステムコーポレーションが取り上げられました。詳しい内容を知りたい方は、ぜひ下記のYouTube動画をご覧ください。
ノムラシステムコーポレーションの紹介動画
お問い合わせはこちら